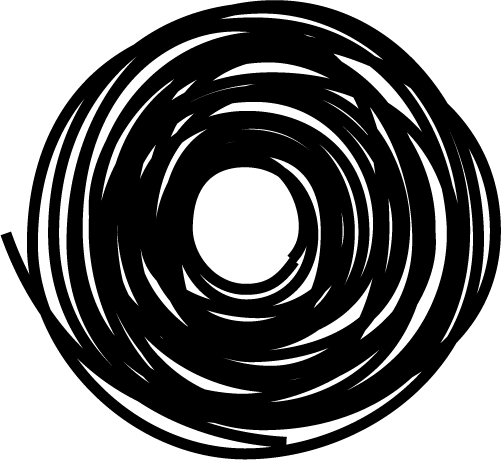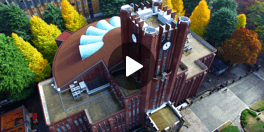July 19, 2024
【教員インタビュー】目黒公郎教授 (前編)Faculty Interview: Professor Kimiro Meguro, Dean of the III/GSII (Part1)
2024年度に新学環長・学府長に就任された都市災害軽減工学がご専門の目黒公郎先生のインタビューです。
本インタビュー記事は、前編と後編に分けて掲載します。前編は、令和6年能登半島地震をはじめとする災害対応の課題について、後編では学環・学府の今後の課題と展望をお話しいただいた内容を紹介します。
(目黒先生のご研究について紹介した2023年の教員インタビューもあわせてお読みください)
(目黒先生のご学環長のメッセージはこちら)
The following interview was conducted with the newly appointed Dean of the III/GSII, Prof. Kimiro Meguro, whose field of research is urban disaster mitigation engineering. Part 1 deals with disaster relief, particularly in relation to the Noto Earthquake that occurred at the beginning of 2024. In Part 2, Dean Meguro explains his vision for the future of the III/GSII.
(Readers may also be interested in an earlier faculty interview conducted in 2023, where Prof. Meguro talks in more detail about his research.)
(Message from the Dean: https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/about/message)
*日本語は抄訳に続く(Japanese interview text follows English summary)
Part 1
Dean Meguro has been playing an active part as an advisor in disaster relief following the Noto Earthquake. He identifies several issues highlighted by this earthquake. First, it demonstrated the special challenges of disaster recovery in a mountainous peninsula, where overland access is limited to narrow coastal routes vulnerable to damage by tsunamis and landslides, the rugged terrain provides only limited landing space for airborne transit, and port facilities for ships are compromised by land uplift caused by the earthquake. In addition, much of the region’s population live in isolated close-knit mountain communities, with large numbers of elderly people who have a strong connection to the land where they live, making them reluctant to evacuate to safer locations more accessible to the relief effort. Local governments are charged with responsibility for the relief effort, but small towns and villages often lack sufficient personnel with suitable know-how to mount an effective response. In many cases, they do not even have personnel permanently assigned to disaster management and must rely on part-time staff or those seconded from other areas of responsibility. Such local authorities also face the additional challenge of providing relief to a low-density population scattered over a wide area, which is significantly more difficult than providing for a population of the same size concentrated in a small area. Small local governments are also ill-equipped to administer the sudden influx of personnel, materiel and funds from outside that occurs after a disaster.
Considering all these challenges, the whole institutional structure for disaster relief needs to be reconsidered. Instead of expecting each local government to be self-sufficient in its disaster response, it would be far better to organize on a broader scale. According to existing legislation, prefectures are supposed to step in when cities, towns and villages cannot respond adequately, but even then, governors tend to attempt self-sufficiency within their own prefectures. It is necessary to set up broad assistance networks, where, for example, disaster victims requiring care can be moved temporarily to suitable facilities outside their usual area of residence.
Recent disaster experience has revealed significant problems both in the provision of assistance from outside and its receipt by disaster-stricken areas. When a major earthquake struck Kumamoto in 2016, the central government took the unprecedented step of proactively anticipating likely needs and sending aid to the stricken area, rather than waiting for requests for help from the local authorities. However, there are no clear criteria for deciding whether or not to adopt such “push-type” assistance and many complications occurred in the process of implementation. Often those receiving the aid were not clearly informed about when and where the aid would arrive. The content of the aid was also problematic in some instances. For example, when the central government decided to send three-days’ supply of ready-made meals for 100,000 people (the number of people estimated to have been affected by the earthquake), they placed orders with suppliers near Tokyo, giving rise to problems of delivery which would not have occurred if the meals had been provided by suppliers closer to the earthquake-stricken area. In order to avoid such problems in the future, Dean Meguro has proposed the creation of a map detailing the capacity of each region to supply the necessary goods in case of a disaster.
On the other hand there are deficiencies in the ability of disaster-stricken areas to receive the aid sent to them. After the Kumamoto earthquake, local authorities complained that their facilities were taken over by personnel from the central government, thus hampering their own disaster response. However, this simply reveals a lack of proper planning about what facilities should be reserved for whom and what tasks should be assigned to whom in the case of a disaster. Furthermore, local government personnel may lack sufficient expertise in the running of evacuation centers. Where personnel are scarce, it would be better to concentrate their efforts on tasks only they can do. Daily management of shelters can be more effectively entrusted to experienced volunteers among the evacuees themselves, with the additional benefit of promoting self-reliance. Likewise, warehouses for the storage of emergency goods need to be properly managed so that the items needed most immediately are easily accessible.
―目黒先生は地震をはじめとするハザードが社会に与える障害の最小化、および災害発生時を地域の潜在的な課題を改善する機会として有効活用するための、ハードとソフトの両面の対策に関する研究をされています。これまでも国内外の多くの災害現場へ足を運ばれていますが、1月1日に発生した能登半島沖の地震ではどのように動かれたのでしょうか?
今回私は後方支援に回り、現地入りして活動する仲間や関係省庁、地方自治体の皆さんに、今後発生が予想される各種問題への配慮や対応についてアドバイスするなど、復旧・復興に向けた活動がスムーズに進むように動きました。
地震が起きてすぐに思ったのは、半島という地形の特徴から来る災害支援の難しさです。半島でなければ、普通はいろんなルートから現場にアクセスできますが、半島の場合は陸路でのアプローチでは陸地と繋がっている部分からのみになりますし、一般的に半島の中央部は山地や森林であることが多いので、道路は海岸線に沿って整備されます。しかし海岸線に沿った道路は津波の影響を受けるし、切り立った海岸線では土砂災害の影響も受けやすい。結果として、孤立集落が発生しやすくなるのです。これは能登半島だけの問題ではなく、南海トラフ地震が発生した際の紀伊半島や、東海地震の際の伊豆半島も同様です。
このようなケースでは、空路や海路でのアクセスが重要になるわけですが、狭い半島では広いオープンスペースが少ないので、ヘリコプターなどによるアクセスが困難になる場合も多いし、今回の地震では、海岸部が隆起したので海からのアクセスも難しくなりました。さらに能登半島地震は真冬に起こったので、地震後の寒さや積雪対策も重要になります。加えて、少子高齢、人口減少も進んでいる地域ですし、その土地に代々住み続けてきた方が多い地域なので、土地への愛着や仲間意識の強さなどから、他地域の人々による被災地支援には困難が伴うことも予想されました。
私は被災地の早期の復旧・復興のためには、ケアを必要とする被災者の皆様には大変申し訳ないが、コミュニティーを保持できるような配慮をした上で、被災地から離れた環境のよいところ(例えば、温泉があるような場所)にしばらく疎開していただくべきだと伝えました。
これは被災者自身の生活環境の改善に加え、そうしないと、被災地の厳しい環境下で被災者のケアが求められるので、被災地に投じられる資源の有効活用が困難になり、復旧・復興が遅れてしまうからです。ケアを必要とする被災者の人たちに被災地外に移動していただければ、ボランティアの人たちを含め、ケアの体制を作って動くことに集中できます。
しかし、こういった提案は当初はなかなか受け入れられませんでした。災害対応の主体はまずは被災市町村、この対応力を超えた場合には都道府県が対応するという現行制度に対して柔軟に対応できなかったためです。現行の災害対策基本法の中では、災害対応の責任はまずは市町村長が持ち、その次が都道府県知事になりますが、残念ながら現在の日本の市町村の多くには災害対応を担う人材もいなければ、ノウハウの蓄積もありません。この背景には構造的な問題があります。
平成の市町村大合併のために、昭和の末に3,400ほどあった市町村が、今は約半分の1700余になっています。それぞれの人口ごとに見ると、日本の市町村の85%は10万人以下、3万人以下が53%。1万人以下は約3割です。一方、市町村の役場の職員数は、市町村民100人に対して1人ぐらいが平均なので、人口100万の都市の職員数は1万人、人口10万人であれば1,000人。1万人の市町村では100人ということです。一方で、市町村はその人口の大小に関係なく、等しいサービスを提供しなくてはいけない。つまり、職員の数が減っても、同じ数の部署や係を持つ必要があります。ゆえに、人口の少ない自治体では各部署や係に人を割り当てるのは無理なのです。結果として、現在500近い市町村では、災害対策や危機管理部門に所属する専任の担当者が一人もいない状況です。さらに、平成大合併は職員数の削減という意味もあったので、合併によって、およそ15%の職員数を減らしました。人員を減らしても仕事がなくなるわけではないので、その分はアウトソーシングと称して外に切り出したわけです。それらの仕事は、パートタイムの人たちにお願いしているわけですが、そういう人たちが自治体職員として働いている人たちと同じように災害対応を担うのは厳しいはずです。
それから、人口密度が低い場合、同じ規模の地震や台風が襲ったときに被災する人々の数は確かに少なくなります。しかし、対応する側から見れば、同じ100人が被災するときに一か所に固まって100人が被災するケースと、過疎化で分散して住む人々が100人被災するケースでは、大きな違いがあります。また、土砂災害や道路、水道などの被害では、エリアが広ければ広いほど被害は多く発生します。このような状況なので、市町村長がまずは責任を持つという現行制度は、本質的にうまくいかないのです。
東日本大震災の災害対応でも同様でしたが、人口規模が小さな自治体が被災すると、災害対応部局に専任の担当者が1人もいなかったり、兼務を含めごく少数の担当者しかいない状況で、膨大な災害対応業務をこなさなくてはいけない状況になります。復旧工事額も、自治体の年間予算の何倍にもなるわけですが、そんな規模の予算を扱ったことのない職員が対応することは容易ではありません。また、外部から多くの人が業務の支援に来ますが、大人数の管理などしたことのない職員はその対応に窮してしまうのです。
このような構造的な問題を踏まえると、今後の大規模災害における災害対応や復旧・復興活動は、人口の少ない市町村にとっては、今後悪化することはあっても良くなることはありません。そういう観点から、私は災害対策基本法を変えるべきだと訴えているのですが、簡単ではありません。
現行法では、市町村単位での対応が難しい広域災害が発生した場合は、都道府県知事が責任を担いますが、そうなった場合、知事は自分の都道府県の中で何とか完結したいと思いがちです。私は今回、被災県内で完結する支援ではなく、もっとずっと広い範囲での支援を考えるべきであることを訴えました。ケアの必要な被災者が安心して過ごすことのできる場所で、被災者を受け入れてくれる自治体を広く募って確保するので、そういった場所で一定期間過ごしてもらうようにすべきであると、関係各所にずっと働きかけていました。一気に舵を切るのは簡単ではないですが、重要なキーパーソンに、こういった提案を直接できるネットワークを持つ人間もあまりいるわけではないので、私に期待される貢献かもしれないと考えて、今回は後方支援に回ったのです。自分が実際に現地に行くことも大切ですが、交通が混乱したり救援物資の搬入などで忙殺されている現地職員に迷惑をなるべくかけないで、後方で私ができることは何かを考えての行動です。
―被災自治体の能力を超えた災害が起こった時の災害対応のあり方としては、専門家集団が指揮系統を担うことがよいということでしょうか。
もちろんそうですが、現状では、支援する側と支援を受ける側の双方にさまざまな課題があります。2016年に起こった熊本地震の対応を例に取ると、あの時は政府が熊本県庁に現地対策本部を作って、霞が関の関係省庁から人材を出して、彼らがリエゾンとして熊本県を支援しました。この地震では、日本で初めて「プッシュ型災害支援」といって、「被災地の要望を聞かずに、霞が関が被災地のニーズを予想したうえで支援物資や人を送り出す」ことをしました。後に私は、内閣府の本府参与として、この熊本地震の一連の災害対応をレビューしましたが、その結果として、プッシュ型支援を実施するかしないかの判断基準が明確ではなかったこと、物資の調達や発送などを実行するまでの手続きが多く煩雑であったことなど、さまざまな課題が浮きぼりになりました。また、霞が関は物資を調達して、現地に向けて送り出した時点で自分たちの仕事としては基本的に完了と考えたようで、現地からの問い合わせに対して、送り出した物資の所在(時間と場所)を説明できませんでした。なので、現地はいつ何が届くのかがわからず、ずっと待たなくてはいけなかったなど、受け入れに際して大きな問題となりました。この主因は、送り出した物資の所在を霞が関が十分トレースできなかったからです。また、送り出す物資の調達先にも問題がありました。例えば、熊本地震による避難者数を10万人と見積もり、3日間の食べ物90万食(1人1日3食x10万人x3日)を確保し、これを指定公共機関に手伝ってもらって現地まで輸送したわけです。その調達先としては、霞が関が交渉しやすい関東や中部地方の業者を選定しました。なので、現地に届くまでには時間を要し、先に説明した送り出した物資が「今、どこに、あるのか不明」問題も出たし、賞味期限や消費期限の問題も発生しました。しかし、90万食の食糧は九州から問題なく調達できたのです。このような問題を繰り返さないように、私は、様々な物資に関して、各地域でどれぐらいの量を供給できるかを示す「地域別資源供給能力マップ」を作るべきだと提言しました。
一方、被災地側には、支援を効果的に受けられなかったという問題が見られました。被災地外から被災地を支援する力のことを「支援力」といい、それを受け、効率的に活用する力を「受援力」と言いますが、この「受援力」が不足していたということです。熊本県庁の人たちにヒアリングした際には、「自分たちが本来、災害対応のために使うはずだった空間を、霞が関からの支援者が来て乗っとっちゃって、自分たちは不便な場所に移動させられた。また、『あれやれ、これやれ』と指示されるので、本来自分たちがやろうと思っていたことがうまくできなかった」という苦情めいた意見も聞きました。しかし、これは正しい認識とは言えません。霞ヶ関からの支援がない状況で、熊本県だけではあの災害対応ができたかと言えば、これは難しかったわけです。なので重要なことは、外部からの支援者に、災害対応のどこをお願いするのか、支援者にはどこの空間を使って業務をしてもらうのか、彼らの被災地内での生活はどうするのか、などを事前に決めておくことです。先ほどのクレームの本質的な原因は、事前にこれを決めておかなかったことです。
また、熊本地震では、避難所運営や救援物資の対応などに大量の人材を割いたわけですが、これらの業務に関しては、自治体職員が経験や専門性を有しているわけでもないし、そもそも自治体職員がどうしてもやらなければならない仕事でもないわけです。避難所の運営に自治体職員がかかわると、避難所ではどうしても行政と被災者の間に、サービスを提供する側と受ける側の対峙関係が生まれます。人手不足の中で専門性の低い職員が対応するわけなので、行き届かない部分も出てきますが、行政と被災者の関係の中で、被災者にも甘えの気持ちが発生しやすくトラブルが起きることも多い。プロボノと呼ばれる経験の豊富なボランティアを中心に被災者による自主運営を行えば、自分たちの避難所に対する意識も変わるし、甘えの気持ちもなくなります。このようにすることで、行政は職員でなければ対応できない業務に人材を集中することが可能になります。緊急物資の調達における倉庫内での物資の管理なども同様です。備蓄倉庫ごとの設備の内容や備蓄品の管理などに精通しているわけではないので、「フォークリフトをどう使って、どんなふうに荷物をさばくのか」を知りません。事前の検討もされていないので、送られてきた荷物を人海戦術で順番に倉庫の奥から積み上げてしまう、そうすると実際に使う場合に、奥にしまったものなどは出しにくくなってしまいます。あらかじめ、空間配置を設計し、種類別に配置位置や配置法を決めておく必要があるのですが、それが不十分だったのです。
(後編に続く)
企画:学環ウェブ&ニューズレター編集部
取材・構成:山内隆治(学術専門員)・神谷説子(元特任助教)
写真:柳志旼(博士課程・編集部)
インタビュー日:2024年2月10日
主担当教員Associated Faculty Members
教授
目黒 公郎
- 先端表現情報学コース
Professor
MEGURO, Kimiro
- Emerging design and informatics course