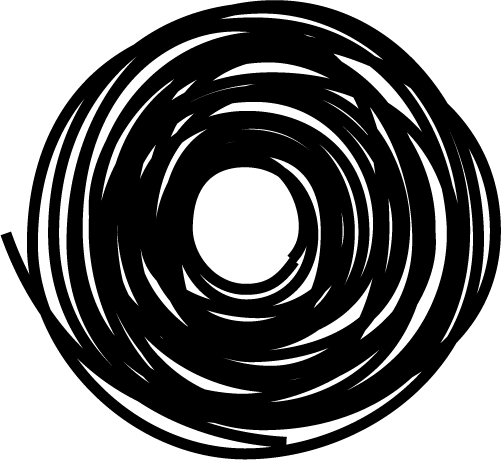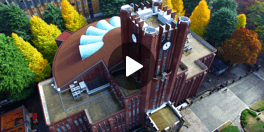September 28, 2020
【教員インタビュー】林 香里 教授(後編)Interview with Professor HAYASHI, Kaori (Part2)
見えない「敵」との戦い
ー 女性やマイノリティの視点をメディアに、そして東京大学に ー
林 香里 教授(前編)
2004年より基幹教員として学環学府を支えてこられた林先生にお話を伺いました。メディアとマイノリティ、特に「ジェンダー」という研究テーマに対する姿勢について伺いました(取材はオンラインで行われました)。
*日本語記事は英文に続く
Battling an Invisible “Enemy”: Media and the University from the Perspective of Women and Minorities
Prof. Kaori Hayashi
Kaori Hayashi has been a core faculty member of the Interfaculty Initiative since 2004. We spoke with her about her research on media and minorities, focusing especially on her stance towards the topic of “gender” (The interviewed was conducted online).
(Part2)
In Part 2, Professor Hayashi answered questions about her views on gender and the role of diversity in academia.
She points out that gender is one of the fundamental categories around which society is organized. Gender roles tend to be unquestioned, and any attempt to rethink them, and especially to question the gender binary itself, means rethinking society as whole. Thus, while many people pay lip service to the importance of promoting the role of women in society, there is a tendency to shrink back from taking action when faced with the radical implications. The problem of gender discrimination is structural. It is a hidden “enemy” which persists despite the predominantly good intentions of most individuals, both female and male.
As an assistant to the university president, Professor Hayashi is currently playing an active role in the formation of university-wide policy on internationalization and diversity. One of the most important tasks in this area is correcting the severe gender imbalance among the University of Tokyo’s undergraduates. Not only do men outnumber women by four to one, but a very large number come from a few prestigious Japanese private high schools. The undergraduate student body is thus very lacking in diversity, largely excluding not only women but also students from outside Japan. Changing the entrenched system that has led to this situation is a major task.
Officially, men and women compete on equal terms in the academic profession. Especially among younger women, there is a tendency to downplay the fact of being a woman because it would imply recognizing one’s own weakness. Professor Hayashi hopes nevertheless that all younger scholars, both men and women, will not forget the central role that gender plays in society. She herself did not start speaking directly from her position as a woman until later in her career. Seeing how little has changed in the time since she embarked on this career path, she feels some regret about not speaking out earlier. Having now attained a senior academic position, her current work to promote diversity and gender equality are partly an effort to make up for this earlier failing. (Interview Part 1)
— 「ジェンダー」というテーマに取り組む姿勢について教えてください。
子どもが生まれたら、まず「男の子でしたか?女の子でしたか?」って聞くでしょう。「ジェンダー」というのはそれくらい社会的語りの中で自然化されたもので、実際、この社会をカテゴリー化する基本的な枠組みです。男女のあるべき姿を組み替えたり、男女という二分法に疑問を呈することは、すなわち社会全体のあり方を問うことになる。つまり、とてもラディカルな企みです。他方で、日本の社会には男性優位の価値観が厳然としてあって、男性性を肯定する価値に手を突っ込むことは、既存の秩序を否定することにつながります。こうなると、話のレベルでは「女性の参加はいいね」と言ってくれる人も、具体的な議論になった途端に「やっぱりそれはちょっと過激…」とか「女性にはいい人いないんだよね」みたいな話になって、女性がたくさんのポジションから遠ざけられる。そういう場面をいろいろなところで見てきたし、経験もしてきました。
男性の役割と女性の役割を見直すことは、そういう社会革命みたいな含意があるわけです。これは個人の問題というより、制度に関わること。したがって、「敵」はマッチョでわかりやすいいわゆる「おじさん」たちだけではなく、不透明で見えにくい、構造的差別なのです。東大の男性の先生たちも1人1人はジェントルマン。でも、大学や学問の制度のなかに男性的価値観が入り込んでしまっていて、この部分の変革には時間もエネルギーもかかります。
— 東京大学全体のダイバーシティ戦略にも関わっていらっしゃいます。
総長特任補佐という役職で国際化とダイバーシティを担当しています。東大の学部生、大学院生たちをどうやって国際化するのか。東大の学部生のいびつな男女比の割合(学部は男女比8:2)をどうするか、が、私に与えられた任務です。
どちらも、問題状況が似ています。つまり東大の多様化という課題。東大の学部生は特定の私立中高一貫校出身者の割合が高く、かなり均質的な集団です。しかも、教員も含めて多くの人はこの状態こそが「エリート校」の証だと思っているフシがある。東大は表向きは「女性も外国人も歓迎」なのですが、しかし、女性や外国人のなかでも東大という制度文化に適合する人のみを歓迎していて、自らが変わろうという意思がまだまだ足りない。過去の東大を全部そのままにした上で、女性と留学生を増やそうと言っても無理な注文だと思います。組織文化と風土が変わっていかなければいけないけれども、内実はなかなか変わらない。変われない。
— 「ジェンダー」という人間のアイデンティティに関わるテーマを扱うときには、「結局、自分自身の生き方を問わざるを得ない」とも指摘されています*。
少なくともタテマエでは、研究者という職業は、女性、男性に関係なく専門分野でトップを争うもの。それなのに「女性」という立場に対する社会的抑圧について語るのは、自らの弱さを認めるようで、相当のプレッシャーと覚悟が要ります。少なくとも、私はそうだった。だから、これから先、研究者として長いキャリアを歩む30代40代の女性に「なんでジェンダー研究やらないの?」と軽々しく要求することは私にはできません。けれども、先に言ったとおり、ジェンダーというカテゴリーの根源性とその重要さについては、忘れないようにしてほしいと思っています。そしてもちろん、この姿勢は女性に限ったことではありません。
私の場合、30代40代はビクビクしていて、自分は女性である前にあくまでも研究者だと思いたくて、自分の中の「女」を語りたくなかった。私は41歳でようやく就職できたので、あっという間にいわゆる「シニアの教授」とか言われるような年になっちゃったわけですが、最近は、もうそろそろ、「女」のままで語ってもいいかなと突き抜けちゃったところがあります。そして、この地点でふとふり返ったら、保育園の問題とか、学生や教員の女性比率の問題とかが、私が東大に入った2004年の時からほとんど変わっていなかった。いま、そのことにすごく申し訳ない気持ちがあります。おかげさまで私は東京大学の教員という、特権的なありがたいポジションにいる。そのことはいつも自覚し感謝していて、私のような特権的な人が、世の中の不平等や不条理にも気づかず、あるいは気づいたとしても正直に勇気をもって意見を言わないのだったら、この社会は終わりかなって思うのです。だからもう言いたいことを言おう!と思って昨年末にはMeDiの仲間と『足をどかしてくれませんか』なんていうタイトルで本を出版しました。
— 学環学府20周年記念「オープンラボウィーク」のキックオフイベントでは、“diversity elevates academics”というメッセージが印象に残りました。
メディア研究だけでなく、おそらくあらゆる研究分野では、「あたり前」を疑うことが学問の出発点だと思うのです。たとえば、今進めている国際比較研究でも、日本人とイスラエル人とフィンランド人が持つ「ニュース」のイメージはかなり異なります。国際チームで共同研究をすると、普段何気なく使う言葉についてもすぐに社会科学的な議論が始まるんです。あたり前を根本から組み替えていく、つまり「脱構築」作業が必要で、だけどそれは学問にとっては非常に重要なことなんです。セクシュアリティやエスニシティが異なる人たちが集まると、それぞれに世界のものの見方が異なり、解明方法も多様だということをいっぺんに知ることができる。多様な出自や文化をもつ人たちと一緒に学んだり働いたりして、最終的に自らも変化していく―これこそ「認識の発展」と呼ぶんだと、一人でも多くの人たちが実感し納得してこそ、情報学環も東京大学も本格的に変わっていくのだろうなと思います。
(前編を読む)
*林香里 編著、小島慶子、山本恵子、白河桃子、治部れんげ、浜田敬子、竹下郁子、李美淑、田中東子 著『足をどかしてくれませんか。-メディアは女たちの声を届けているか』(2019年、亜紀書房)
企画:ウェブサイト&ニューズレター編集部
取材:鳥海希世子(特任助教)、安ウンビョル(博士課程)
英文:デイビッド・ビュースト(特任専門員)
主担当教員Associated Faculty Members
教授
林 香里
- 社会情報学コース
- アジア情報社会コース
Professor
HAYASHI, Kaori
- Socio-information and communication studies course
- ITASIA Program