教授
林 香里
Professor
HAYASHI, Kaori
- 社会情報学コース
- アジア情報社会コース
研究テーマ
- ジャーナリズム研究、マスメディア研究
- 区分:
- 学内兼担・課程担当教員
- Socio-information and communication studies course
- ITASIA Program
Research Theme
- Mass Media and Journalism Studies Comparative Media Studies: Reports on Fukushima
- Position:
- Affiliated Faculty
- 略歴
博士(社会情報学)(東京大学)
1963年 名古屋市生まれ
1987年 南山大学外国語学部 英米科 卒業
1988年 ロイター通信東京支局 勤務 (~1991年)
1995年 東京大学大学院 社会学研究科 社会学(B新聞学) 修士課程修了
1993年 ドイツ、エアランゲン・ニュールンベルク大学 留学 (~1996年)
1995年 東京大学大学院 人文社会系研究科 社会文化研究専攻 社会情報学専門分野 博士課程 (~1997年)
1997年 東京大学社会情報研究所 助手 (~2000年)
2001年 東京大学大学院 人文社会系研究科より、論文博士号 (社会情報学) 取得(7月)
2002年 10月より、ドイツ、バンベルク大学 社会学講座2 客員研究員(アレクサンダー・フォン・フンボルト財団研究奨学生)(~2004年2月)
2004年 東京大学社会情報研究所 助教授
2004年 (組織統合に伴い) 東京大学大学院 情報学環 助教授
2009年 東京大学大学院 情報学環 教授
- 主要業績
- 学環の研究事業
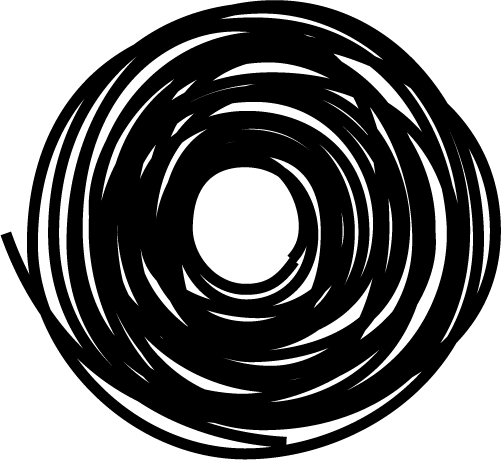


いま、マスメディアは大きな転換期を迎えています。それはインターネットの普及によって、プロのジャーナリストでなくとも、だれでもどこからでも比 較的安価で容易に情報発信が可能になった新しい情報環境の影響があります。しかし、現在のマスメディアの転機は、それだけが原因ではありません。新聞やテ レビなどの、いわゆるマスメディア・ジャーナリズムの転機の訪れは、社会全体の変動、つまり社会の細分化、複雑化、グローバル化によって、私たちがかつて ほどナショナルなコミュニティを単位として共通の社会問題を認識したり、共有したりできなくなっているという社会状況そのものにも求められると思います。 「マスメディア/ジャーナリズム研究」は、マスメディア/ジャーナリズムを研究対象とする学問ですが、対象が変革期にあるならば、当然学問の方法論も変わ らざるを得ません。私たちと新しい規範・倫理の理論に裏打ちされたメディア研究を考えていきませんか。
以下、近年の主なテーマです。
1) マスメディア・ジャーナリズムという職業について:
マスメディアを志望する若者はどのような希望をもっているのか。ジャーナリストという職業は歴史的にどのような経緯で確立してきたのか。増加するフ リーランスや契約社員として働く記者や制作者たちの処遇をどうするか、などを国際間の比較も含めて職業社会学的に観察しています。
2) トランスナショナルな公共圏をいかに捕捉するかについての検討:
近代に発達した公共圏は、17世紀に誕生した近代主権国家の枠の中で発達、形成されてきました。さらにジャーナリズムの主要媒体であるマスメディア という産業も19世紀というナショナリズムが高潮に達した時期に急成長を遂げました。ところが、近年はナショナルな枠組みだけを見ていては公共圏の意見形 成過程は捉え切れません。こうした現象について、報道分野だけでなく、ドラマやバラエティなどの大衆文化も含めて、個別の事例をもとに理論的、実証的な研 究を試みています。
3) アジアのマスメディア動向のリサーチ:
内外で活躍するアジアを中心とする国際的ジャーナリストを招待して講演会や実務的なワークショップを開催したり、ゼミで海外のメディア動向リサーチに出かけたりします。
私の研究室にはさまざまな国籍の学生がつどっています。出身国のマスメディアのシステムや制度について相互に比較検討したり、海外のジャーナリスト を招待して話を聞くワークショップを開催したりして、互いに知的刺激を与え合い、切磋琢磨しています。巷には「マスコミ批判」はあふれるほどたくさんあり ますが、いまいちど、マスメディアとは、そしてジャーナリズムとは社会にとって何か、をグローバルな単位で理論的に分析してみませんか。