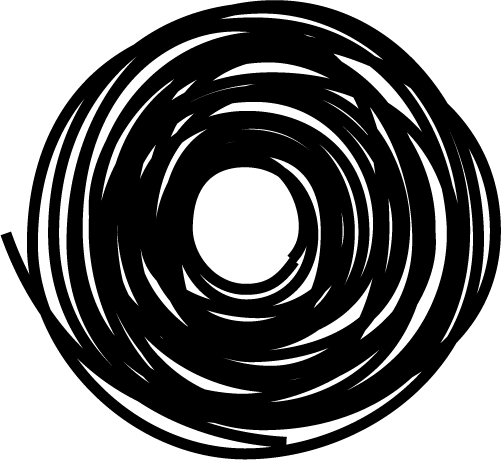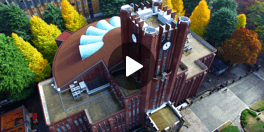February 2, 2023
【教員インタビュー】吉見俊哉 教授(後編)An Interview with Prof. YOSHIMI Shunya (Part 2)
3月末で定年退官される吉見俊哉先生へのインタビュー、後編では吉見先生の研究者としての歩みを中心に伺っています。最後に学生のみなさんへのメッセージをいただきました。
In the second part of the interview, Prof. Yoshimi answered questions about the development of his own research interests. He also had some words of advice for students and younger scholars. (前編はこちら/Continued from Part 1)
*日本語は抄訳に続く(Japanese interview text follows English summary)
An English Summary of an Interview with Prof. Shunya Yoshimi (Part 2)
During his undergraduate years on Komaba Campus, Prof. Yoshimi’s passion was theater. He was more engaged in the activities of the student theater group than in studying. However, over time he became interested in the complex interaction between performers, audience and venue, such that no performance of the same play would ever be exactly the same. From this he developed a unique dramaturgical approach to the study of cities, specifically the popular entertainment districts of Tokyo (sakariba) where people interact in a manner not dissimilar to actors and spectators in a theater. This became the basis for his master’s thesis in the field of urban sociology, which was later published in book form as Toshi no Dramaturgy (Urban Dramaturgy) in 1987.
After his appointment to a faculty position in the Institute of Journalism and Communication Studies (a precursor to the III/GSII), Prof. Yoshimi’s research shifted from urban studies to media studies. He became especially interested in the telephone as an interface between public and private space, the city and the household. At that time in the late 1980’s, telephones were still predominantly wired devices fixed to specific locations, but he foresaw a time (which has since come to pass) when small portable wireless devices would erode the division between public and private spheres as people carry on their private conversions by cell phone while walking the streets.
With his background in urban sociology, Prof. Yoshimi then turned his attention to forms of media that had been embedded in urban spaces, such as outdoor street televisions (common in Japan before the era of universal domestic television ownership) and cinemas. His exposure as a student to structuralist and post-structuralist theory also encouraged an interest in popular culture and power relations, leading to his studies on exhibitions and theme parks. While conducting research on Disneyland, he became concerned with the role of American culture and American power in Japanese society, leading to a focus on American military bases in Japan.
The label of “cultural studies” was only applied to this research retrospectively following a symposium held in 1996 to which members of the Birmingham school of cultural studies, including Stuart Hall and David Morley were invited. This introduced the concept of cultural studies to Japan, and Prof. Yoshimi came to be known as one of its leading exponents in the country. Cultural studies had initially been viewed by media researchers in Japan as just another form of audience studies but gained popularity after the symposium once the full impact of its concern with culture and power came to be appreciated.
The encounter with cultural studies brought two major changes to Prof. Yoshimi’s work. The first was internationalization. He became involved in the launch of the journal Inter-Asian Cultural Studies together with researchers and activists in Taiwan, South Korea, the Philippines and China. He also started using English more freely as a medium of academic communication. Increased exposure to overseas scholarship gave him new perspectives on his own work and provided impetus for his later involvement in the creation of international programs at the University of Tokyo (ITASIA and GLP-GEfIL).
At the final session of the 1996 symposium, the organizers, including Prof. Yoshimi himself, were criticized for not allowing students to participate on an equal footing to established scholars. This, it was pointed out, was contrary to the bottom-up spirit of cultural studies. In response, Prof. Yoshimi helped to facilitate a series of student-led international cultural studies symposia. These events, held in the early 2000s, came to be known as the “Cultural Typhoon” (partly because they were held during typhoon season and were consequently disrupted by bad weather). This was the second major change brought by the encounter with cultural studies.
In 2017, after finishing his term as Vice President, Prof. Yoshimi was a visiting scholar for one year at Harvard University. Since then, he has refocused his research on his original interest in urban studies. Indeed, there is a sense in which he had never departed from this basic orientation, since all the topics he has covered since then are linked in some way to this origin point. It is as if urban studies were located at the center of an ellipse surrounded by numerous other topics toward the edges. To develop one’s research, it is necessary to be open to the neighboring territories instead of focusing exclusively on the center. Each turn in his career has brought about fresh encounters with neighboring territories. His appointment to the Institute of Journalism and Communications Studies brought him into contact with media studies. This in turn cleared the way for the encounter with cultural studies. His later appointment as Vice President also led to an interest in research on universities. Despite their apparent diversity, the various topics addressed in Prof. Yoshimi’s 40-year research career can all be traced back to his early dramaturgical studies of the city.
Prof. Yoshimi offers the following three points of advice to students and younger scholars:
(1) “Talent is persistence.” Rather than being an inherent property of certain individuals, talent is something realized through the persistent pursuit of a particular topic. Once students have decided their research topic, they should be persistent with it. Although they may be permitted one change of topic, they should not change it a second or third time. At the same time, they should not become too narrowly concerned with that one topic but always retain an openness to connections with neighboring topics.
(2) “Talk to people before becoming lost in your own thoughts and listen before talking.” There is much more to research than simply giving voice to one’s own thoughts. Research is fundamentally about building understanding with other people. Even while having one’s own individual focus, one must always maintain communication with others and take an interest in their topics too. Developing one’s own thought involves interaction with others.
(3) “Don’t be afraid to go back to zero.” It takes time and effort to find out what is most important. Sometimes, one may even have to turn one’s back on years of study to find the right path. The experience of difficulty and failure can be beneficial. Even if one is unsure whether the current is path is right, it is better to go forward bravely.
– 吉見先生は駒場の教養学部教養学科の相関社会科学の1期生ですね。学生時代のご様子をお聞かせください。
入学当初、私の学生生活の最大関心事は、勉学ではなくて演劇であり、そして都市でした。私は演劇青年で、駒場にいた頃は演出家の如月小春さんの劇団で一緒にやっていました。演劇との出会いが学問をやろうと思った最大の理由です。
– 演劇から学問に。どのような筋道が見えたのでしょうか。
演劇は、同じ台本を同じ役者が何度も上演しますが、観客や役者の微妙な絡みなどの違いで毎回違うドラマが成立します。同じ言葉を同じ身体が演じながら、そこに違うドラマが成立していくということは、すごく面白いと思いました。言葉と身体と場所、他者のまなざしがとのような関係性の中で、ドラマを成立させているのかということを考えるようになりました。そして同じことが演劇の場だけではなく、都市や社会の中にたくさんある、都市という舞台で成立しているのは一種の演劇であると考えるようになりました。それならば、都市の中で、どのような身体、空間、言葉、イメージによってドラマが成立しているかを考えよう、というのが私の原点です。
その都市のドラマトゥルギーを考える上で一番適している場所は、盛り場だろうと考えました。住宅地だと家庭のドラマになってややこしい話になる。一種の舞台性を持った都市の盛り場に注目してドラマがそこにいかに演じられていくことになるのかを考え、演劇の中で自分がずっと考えてきた問題の延長線上で考えていくことにしようと思いました。学生時代の10年のうち、前半は演劇のことしか考えていませんでしたが、後半はそれまでの都市社会学とは違う都市研究を、上演論的なアプローチによって社会学の地平に出現させていくことができるはずだと考え、修士論文は見田宗介先生のもとで『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂)につながる研究をしました。
– その後、新聞研究所の助手としてキャリアを始められますね。研究対象を都市からメディアにどのように広げられたのでしょうか。
修士論文をバージョンアップする形で『都市のドラマトゥルギー』が出版されたのが1987年。その出版の直前に、杉山光信先生にお声がけをいただいて新聞研究所の助手になりました。当時の新聞研からすれば、新聞学の院生でもなく、都市と大衆文化を研究してきた私は完全によそ者でした。でも新聞研を遡ると日高六郎先生や、当時まだいらした荒瀬豊先生のように、大衆文化的なことを研究されてきた系譜は確かにあり、私はそこに当てはまりました。採用されてみると新聞研は居心地の良いところで、小さいけれどアットホームな、割と自由で融通が効く研究所でした。
当時の新聞研ではニューメディアの研究、特にケーブルテレビジョンの研究をいろんな先生がそれぞれ違う視点から一生懸命やっていらっしゃった。それから高度情報社会の研究も。でも私は面白いと思いませんでした。仕方なく2、3の論文は言われて書いたけれど、面白さがよくわからない。メディアの研究だったら本当はテレビを対象にすべきだろうけれど、今までテレビの研究を何もやってきてないのに、すぐにはできないな、みんながやってないメディアの研究で一番面白そうなのはなんだろうと考えたときに、それは電話だと思いました。
当時はまだ有線電話の時代で、コードレスホンなんていうのはごく一部の人しか持ってなかった頃です。電話は家庭空間の中に大体置かれていますが、そこに声という形で他者が入ってくる。つまり、電話は都市と家庭、親密圏と公共圏、親密圏と都市的な世界の境界線にある。これを考えることは社会学的に面白いと思いました。その頃、新聞研でラジオの研究をしていた水越伸さんと出会い、都市社会学者の若林幹夫さんにも声を掛けて、3人でトヨタ財団から助成金をとって電話の社会学的研究を始めました。1988年からはじめて、何年か続けてまとめたのが『メディアとしての電話』(弘文堂)です。
この本の中で私は、今はとても信じられないだろうけど、いずれ小さな携帯の無線の電話をみんなが持って、街中で独り言のように喋りながら歩く人間が出てくるかもしれないということを書きました。どんどん公共の空間が家庭の中に入ってくるのであれば、逆に私的な空間が外に出ていくこともいずれ起きる。家の中の電話線のコードがどんどん長くなって、いずれそれはコードレスになっていく。コードレスになった先には、その電話が都市に出ていき、個人と個人をダイレクトに結びつけるメディアになっていくということは、ロジカルに見える。でもそこまでわかったら、私自身は電話の研究はもう十分かなと思いました。電話の研究は、多分新聞研に採用されていなければやっていなかったと思います。
この頃から私はメディアといえば街頭テレビや映画館など、都市的な場、盛り場的なものに関心が向いていき、都市の研究者から都市とメディアの社会学者になっていきます。『都市のドラマトゥルギー』で考えていた盛り場のことの延長線上として、都市の演劇性と権力的な作用がどう絡んでいるかということに一番関心がありました。つまり大衆文化的な事象と、その社会的な権力の作動というものがどう絡んでいるかに関心があった。学生の頃に社会学の本だけでなく、ミシェル・フーコーやロラン・バルトなど、構造主義、ポスト構造主義の本をたくさん読んでいましたから、頭がそうなっているんですね。
権力と身体、あるいは人々の感受性がどう絡まり合っていくかを文化の現場の中で考えようとすると、例えば博覧会のようなナショナルイベントは、文字通り権力がそこに作動し、大衆が動員されていくわけですからその問題がよく見えてくるはずということで、しばらくは博覧会の研究をして、『博覧会の政治学ーまなざしの近代』(中公新書)にまとめています。その後はディズニーランドを研究しました。文字通り、グローバルな権力と、それに踊らされていく身体が文字通り一番重なっている場所なのではないかと考えました。ディズニーランド研究でも論文を結構書いています。
ディズニーランドを研究する上では日本の中のアメリカという問題を考えなくてはいけないですが、でも、ある時からディズニーランドだけでは日米関係の文化的な権力構造は捉えきれない、やはり米軍基地を考える必要があると考えるようになりました。ディズニーランドと米軍基地は表裏の関係にある。浦安のディズニーランドと、横須賀や厚木、あるいは沖縄の米軍基地がどこでどういうふうに繋がっているかを歴史的に考えた。それが『親米と反米』(岩波新書)になっていきました。
私は自分が考えていることがカルチュラル・スタディーズだとは思っていませんでした。私は盛り場と演劇のことを考えており、ドラマの問題を社会の中で考えようとしたときに盛り場っていうテーマが出て、盛り場における権力の問題を考えようとしたときに、博覧会っていうテーマが出て、博覧会の現在形みたいなことを考え、20世紀を考えるときに、ディズニーランドの問題を考えなくちゃいけない、と思ってやってきました。ディズニーランドの問題を考えていけば、米軍基地の問題も考えなくちゃいけないということになっていったわけです。
– 吉見先生はカルチュラル・スタディーズとはどのように出会われたのでしょうか。
1996年に、花田達朗先生に、ブリティッシュカウンシルからの助成金で、バーミンガム大学のスチュアート・ホールや、デヴィッド・モーレーたちを呼んできて、カルチュラルスタディーズを真正面から日本で紹介する大きなシンポジウムを一緒にやろうと誘われました。水越さんも加わってくれて、三人でそのシンポジウムを準備しました。
当時はまだカルチュラル・スタディーズという言葉は全然メジャーではありませんでした。この頃マス・コミュニケーション研究の中でカルチュラル・スタディーズというのは受け手研究のことでした。受け手の能動性というものを強調するのがマスコミ研究の中でカルチュラル・スタディーズでした。そういう理解と、私が考えていたことは結構、距離がありました。でも、このシンポジウムに向けて研究会を開催し、カルチュラル・スタディーズとは何かを学んでいく中で、それが必ずしも受け手研究ではないということがわかってくる。カルチュラル・スタディーズはポストコロニアリズムでもあり、ポピュラーカルチャー研究でもあり、ジェンダー・スタディーズでもあり、要するに文化と権力の問題を考えるということ。私がやろうとしていた問題はカルチュラル・スタディーズだと、後から気づいたのです。この頃からカルチュラル・スタディーズの吉見俊哉というふうにもなっていきます。
カルチュラル・スタディーズに向かっていく過程で、私の中でふたつの大きな変化がありました。ひとつは、私自身が急速に国際化したのです。1996年のシンポジウムに、台湾からホールの下で学んだ陳光興さんという同世代のアクティビスト的研究者が来ました。その時にお会いしたのがきっかけで、彼が準備していたInter-Asia Cultural Studiesという英語の雑誌を立ち上げるプロジェクトに日本から加わることになりました。他には九州大学の太田好信さん、大阪大学の冨山一郎さん、それから武藤一羊さんというべ平連の中核的なメンバーがいらっしゃいました。
このプロジェクトでは、ある時はシンガポール、あるときはマニラ、ソウル、北京、オーストラリアと、海外でミーティングとかワークショップを開いていろんなことをやったので、英語を喋ったり英語でプレゼンする機会が増えました。当初は原稿を作って辿々しく読んでいましたが、あるときから原稿なしで喋ったら、陳光興さんに「吉見、それの方がすごくいいよ」って言われました。それから、あらゆる国際会議で原稿を作らない癖がついちゃった。その場のオーディエンスを見ながら思いついたことを英語で話すわけですが、相手を見たら雰囲気で、ブロウクンな英語でもなんか喋れちゃう。そして相手が何を言っているかもわかるようになりました。昔から比べると英語力が少しはアップしたんですね。
国際的なネットワークの中で仕事をすることは日本の中でいろいろ考えるのとは全く違う。私はこの頃から外から自分を見るということを経験するようになりました。留学はしていないけれど、海外に繰り返し行って英語でディスカッションしたり発表したり、だんだん慣れてくると、だんだん自分の見方も変わってくるというか、外から日本の中の自分を見るようになり、もうひとつの自分がそこに生まれてくるという、すごく重要な経験をしました。この経験が先にお話したITASIAやGLP-GEfILといったプログラムを作ろうという考えにも繋がりました。
この1996年のシンポジウムのもう一つのインパクトは、これがカルチュラル・タイフーンに繋がったことです。シンポジウムの最後は大波乱でした。このシンポジウムの研究会に参加していた若手や学生たちから、総括シンポジウムのときに花田先生と私は糾弾されました。学生たちを研究会に巻き込んでおきながら、最後の舞台のシンポジウムのパネリストに、誰1人学生はいないじゃないですか、エスタブリッシュされた学者ばかりで、それがカルチュラル・スタディーズなんですか?って。
ブリティッシュカウンシルの国際シンポジウムだし、それなりのエスタブリッシュされた方たちをパネリストにするのがいいだろうと私は思っていました。だけどそれがカルチュラル・スタディーズか?って言われると、たしかに反論できないなと思いました。それでこのリベンジとして、学生が徹底的に中心になる国際シンポジウムをやることにしました。国際交流基金からお金をいただいて、2002年に韓国の姜明求先生と私が中心になり、キャラバンのシンポジウムを企画しました。日韓カルチュラル・スタディーズの国際シンポをまず東京でやり、そしてそのまま主要メンバーがソウルに飛び、そこからチンチョンっていう38度線の一番近いところまで行って残りのシンポジウムをやるという企画でした。
どういうわけだか、私がシンポジウムを企画すると、必ず台風や地震がよく起こるんですが、この2002年のシンポジウムの前日にも大荒れの台風が来ました。香港や台湾から飛行機が飛ばないとか遅れるとか、メインのパネリストが遅れるとか、台風にたたられたんですよ。7月の台風シーズンだったと思いますけど。でもキャラバンはすごく成功しました。これがきっかけで「カルチュラル・タイフーン」という名前で、学生中心、ファカルティーは裏方の、学問的、文化的台風を起こしていく、シンポジウムをやっていくことになりました。1回1回過ぎ去っていって、風景が変わっていくカルチュラル・スタディーズのシンポジウム。第1回は早稲田大学で開催し、その後沖縄や下北沢などでも開催され、いまだに続いており学会にまでなりました。そういうことを結構アクティブに2005年までやっていました。
その後の約10年は、学環長、東大副学長として働き、2017年から1年間はハーバードへ行きました。今私は自分の原点の都市研究者に戻っています。この5年ぐらいで書いている本の非常に多くが、都市論です。演劇論的な都市研究者として私は最後の仕事をしていこうと思っていますから、これからますます都市について書く本は増えると思います。
– 吉見先生のこの40数年のお話を伺いますと、10年ごとにさまざまに転換していったようですね。
外から見ると、メディア研究とかカルチュラル・スタディーズとか、あるいは戦後日本論、都市論、あるいは大学論だとかいろいろな違うことをやってきたというふうに見られているかもしれませんが、私自身はずっと過去約40年にわたって一つのことしかしてこなかったと思っています。つまり方法としての都市という、1987年に書いた『都市のドラマトゥルギー』の問題意識から、それほど大きくは変わっていないということです。研究というのは、自分の問題意識、あるいは最初の方向性だけで成り立つわけではない。研究とはある種、楕円的な構造を持つ。自分の側に一つの揺るがない中心点があるが、同時に外からもう一つの中心がやってくる。外からなにかが来たときに、自分の研究テーマはこれで、自分の研究にとってこれは無駄だからやらないと閉じるのはいいことではありません。こだわりすぎるということは、逆に言えば、こだわっているものの幅を狭くしてしまうことだと思います。そうではなくて外から来たもう一つの中心とどう結び合うか、繋ぎ合わされるか、どう結び目を作っていくかっていう課題がそこに浮上するわけですね。
『都市のドラマトゥルギー』で自分なりの中心点を私は見つけましたが、その中心点に対してメディアの研究所に就職したら、メディア研究との結び目を作る。メディア研究というもう一つの中心と、それから私自身が考えてきた都市という中心点で、この繋ぎ目を作ることによって楕円形を描いていく。あるいはカルチュラル・スタディーズというグローバルな流れと出会ったときに、大きな流れの中に身を置きながら、そちらの中心と自分が保持してきた中心点の結び目の中でもう一つ別の楕円を描いてみる。あるいは東京大学なり、情報学環という大学の制度の中で、ある役割を果たさなければいけないという立場に置かれていったときに、そちらの方から来た中心点と自分の中心点の結び目で大学論を展開していくというようなことをいろいろやってきたと思います。私自身がやってきたことは、自分の中心点にあくまでこだわりながらもう一つの中心点も受け入れていくことによって、楕円形で何かを考えていくような営みだったのではないかと思います。
– これから研究に取り組む若い世代の人たちに、アドバイスをお願いします。
大きく3つあります。まず「才能とは執念である」ということ。つまり自分の軸足はずらすなということです。最初から才能がある人間なんて私はいないと思います。しかしあることが好きでものすごくそこに問題意識を持ち、何とかこの問いを命がけで形にしていこうという執念を持ち続けられるかどうかが、その人の研究やその人生を決めていくのだと思います。そういう執念を大切にしていただきたいということです。
私は多くの学生を指導してきた経験上、一度だけは熟慮の上で研究テーマを変えていいが、二度変えてはいけないと言ってきました。最初は何か勘違いしていた、あるいは最初考えが足りなくて、その研究テーマの設定を間違えたということはあり得ます。自分が本当に考えようとしていたことはこういうことだと見えてきたらそれは研究テーマを変えるべきです。でも、同じことをやっていると、他のテーマが面白そうに見えることがある。そこで2回3回と別のテーマに移っていっては何もものになりません。だからといって一極集中的にという、そのことだけに閉じた形でこだわってしまうと、必ず行き詰まります。外から入ってくる視点や別の立場、別の仕事に対して常にオープンであるべきだと思います。
2つ目のアドバイスは「考え込む前に話せ、話す前に聞け」です。自分だけで考えて何かが生まれるということには明らかに限界があります。自分と違う立場、自分と同じ研究テーマでなくても、自分の話を相手にする。あるいは相手の話を聞いて、自分の研究テーマとは関係なくても、その人の研究テーマの中に入って一緒に考えてみることを継続的に行うことはとても大切です。研究は決して自分が信じていることを言葉にすることではありません。相手に理解してもらえることを言葉にしていくのが研究です。自分が思っていることを1人よがりに言葉にしたって研究にはなりません。自分の中心軸はあるべきですが、それだけでは研究は成り立ちません。外側に他者がいる。他者との結び目を見つけていくことの中で初めて言葉が出てくる、研究の言葉が出てきたり、論文が書けたりするので、1人で考え込んではいけないのです。仲間をつくって、お互いに話していくことからまず入ることです。
そして3つ目は「ゼロになる勇気を持て」ということです。それまで積み重ねた研究や読書も、思い切って捨て去ることも、時に必要になるかもしれません。本当に自分は何をやりたいのか、そして本当に自分がやりたいことからすると何が最も重要で、いろいろ時間を使ったけれども決定的なことではないのか、ということをもう1回見直して、場合によっては一旦全部捨てる。それだけの勇気を持って前に進んでいただければ、決して一度勉強したことや、一度経験したことは忘れないと思います。むしろ、様々な失敗とか様々な困難にぶち当たって、もう1回出発すると、今までこだわってきた中心とは違う視点が見えてくるということがあると思います。そうした勇気も持って研究をしてください。
ぜひみなさん、オープンな心、執念、さらに思い切りの良さを兼ね添え、よき研究仲間と、心を開いて話し合う、充実した研究生活を送ってください。
企画:学環ウェブ&ニューズレター編集部
インタビュー:開沼博(准教授)、山内隆治(学術専門職員)、柳志旼(博士課程)
インタビュー・構成:神谷説子(特任助教)
英語抄訳:デービッド・ビュースト(特任専門員)
Interview: Hiroshi Kainuma(Associate Professor), Ryuji Yamauchi(Project Academic Specialist), Jimmine Yoo(PhD. student)
Interview & text: Setsuko Kamiya (Project Assistant Professor)
English summary: David Buist (Project Senior Specialist)
インタビュー日:2022年7月7日、於吉見研究室。追加インタビュー(オンライン):2022年8月25日
The initial interview was conducted in person on July 7, 2022. An addition online interview took place on August 25,2022.
*このインタビューのダイジェスト版をニューズレター『GAKKAN』(NL59号) に掲載しています。
主担当教員Associated Faculty Members
教授
非公開: 吉見 俊哉
Professor