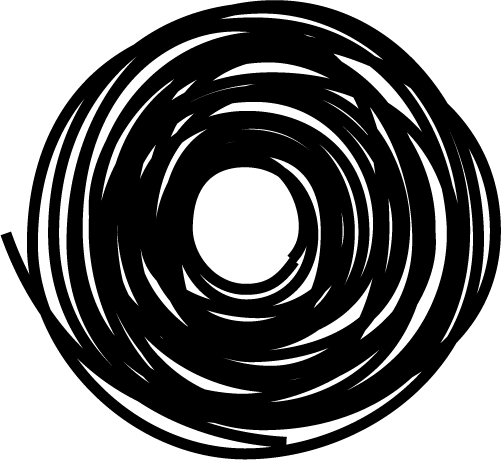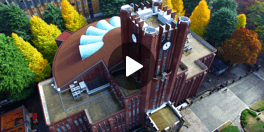November 7, 2023
【教員インタビュー】酒井麻千子&永石尚也 准教授(前編)An Interview with Associate Professors SAKAI, Machiko & NAGAISHI, Naoya (Part 1)
社会情報学コースで法政策領域のご研究をする酒井麻千子先生と永石尚也先生のインタビューです。前編ではそれぞれのご研究テーマとそれに至った背景、そして生成AIと著作権や法哲学について伺いました。(インタビュー日:2023年7月13日)
Machiko Sakai and Naoya Nagaishi are both associate professors in the III specializing in law and policy studies. They teach and supervise students in the Socio-information and Communication Studies Course of the GSII. In the first part of the interview, conducted on July 13, 2023, they answered questions about their respective research topics and intellectual backgrounds, as well as addressing the contemporary issues of generative AI, copyright, and philosophy of law.
*日本語は抄訳に続く(Japanese interview text follows English summary)
Prof. Sakai’s research focuses on the history of copyright law and how it has evolved in response to technological and social changes such as the emergence and widespread adoption of photography. Curiosity about society’s response to the development of such mechanical means of producing images initially stimulated her interest in copyright.
Prof. Nagaishi works in the field of philosophy of law, focusing especially on the impact of advanced technology and new scientific discoveries on legal practice. Two factors led him to this specialization. The first was the 9/11 attacks of 2001 and the difficulties of finding legal justifications for the response to them. The second was the emergence of the concept of “architecture” (associated with the writing of Laurence Lessig and others) as an alternative way of fulfilling the regulatory function of law. Rather than seeing architecture simply as an efficient way to skip the legal process, it is necessary to pay attention to who designs architectures, how they are designed, and what interests or norms become embedded in them as a result.
Having grown up in the 1990s and early 2000s, both Prof. Sakai and Prof. Nagaishi might be described as “digital natives.” However, when asked about the impact of such generational factors on their research they had the following reaction. Firstly, unlike the older generation of “techno-geeks”, they grew up as “lite users” of the new technology rather than as specialists in the technology itself. For Prof. Nagaishi, this meant becoming interested in the impact of information technology on social regulation through surveillance and information gathering after 9/11 and subsequent events including the COVID-19 pandemic. For Prof. Sakai, it meant looking back at an older technology – that of photography – and considering the longer time span of technological impacts on law.
The interview went on to consider the topical issue of generative AI and its legal implications. While recognizing the inevitability of an impact, Prof. Sakai pointed out that the initial response would be one of trial and error using existing law and precedent. For example, the current assessment of copyright claims is based on the criteria of derivation (Is the work in question based on the original work?) and resemblance (Does it resemble the original?). The application of such criteria to the output of an AI will raise difficult questions of interpretation which remain to be worked out. In the future, law will have to be adapted to deal with such issues as whether AI generated content can be copyrighted, and if so, who should own those rights. At present, only human beings are recognized as having authorship. In future, could an AI also be recognized as having authorship? What does this imply about the very concept of authorship? While such questions are not entirely unprecedented and frameworks do exist in which they can be discussed, it will take time to arrive at practical legal solutions. There will also be some feedback between law and policy as this process progresses.
As Prof. Nagaishi explained, legal scholars tend to focus more on how law adapts to new circumstances through interpretation rather than on legislation. That is not to say, of course, that circumstances may arise in which there is a high demand for legislative and policy action to solve pressing issues that may arise. For example, existing law in Japan provides for the use of copyrighted material without the authors’ permission when that use is for “minor” or “non-appreciative” purposes. Whether and how this provision should apply to the use of copyrighted material in generative AI is now a matter requiring consideration. It is important also to recognize that different conditions apply depending on the context and field of usage. Mechanical processing may be more acceptable in some fields than in others. For example, such treatment may be more appropriate in the academic context than in other fields. It is up to researchers in the field of information law to develop concepts whereby such distinctions become possible in practice.
– 酒井先生のご研究について教えてください。この道に進まれたきっかけはありますか?
酒井:情報法の中でも 著作権法を研究しています。特に、19-20世紀の著作権の歴史において、当時の新技術、例えば写真が、その普及や技術発展の中で、著作権法制度に与えた影響、法の解釈や立法過程に与えた影響を検討しています。
自分は写真を撮ったり見たりするのが好きで、色彩の感覚や構図など、同じ場所を撮っても人によって全然違う画になるのが面白いなと感じてきました。他方で、アナログからデジタルへ移行し、写真が身近になり、特にスマホ等で誰でも簡単に写真が撮れるようになった現代、「誰が撮っても同じ」と言われがちなところもあります。また、写真はカメラ、つまり機械を使うので、歴史的に人の手で描かれる絵画や版画等とは異なる存在として扱われてきました。今でも、機械を用いた創作であるという特徴を考慮した法解釈がなされることもあります。こういった写真の取扱い方の特殊性に興味を覚えたのが、著作権法を勉強しようと思ったきっかけの一つです。そして、修士・博士過程では著作権法を対象にすることは決まっていたものの、どの論点を扱うか明確に決まらず、ぐるぐると悩んでいました。そんな中、写真の技術的・機械的側面、そして技術発展を、著作権法は歴史的にどのように評価してきたのか、その過程を検討してみたいな、と思い、実際取り組んでみたら面白くて、これまで研究を続けてきました。
そういった意味では、広く技術と(著作権)法に関心があります。学環にいるので、現代の新しい技術と著作権についてはいろいろ勉強しながら研究しています。
– 永石先生のご専門と、それに進まれたきっかけがあればお聞かせください。
永石:専門は、法哲学という分野です。その中でも、私は「法と科学」と呼ばれるテーマを対象としています。例えば、先端的な技術開発や新規の科学的発見が、法実践に対してどういう影響をもたらすか。とりわけ負の影響をもたらす場合、どういう形でその折り合いを裁判の場でつけてきて、時に折り合いに失敗してきたか。さらには、行政がそれらの不確実性をどういう形で受け止め、コンフリクトを回避するべく介入してきて、時に失敗してきたか……といったところを様々考えています。現下の生成AIに対する(前のめりかもしれない)様々な規制(及びそれをめぐる諸議論)がどのような意味で功を奏するのか、というところも、上記テーマに由来する関心の一つになります。
法哲学の道に入ったきっかけは2つあります。大学入学は2003年ですが、進路選択を考える高1、2年の頃に、米国でいわゆる同時多発テロがありました。事件自体も衝撃的ではありましたが、最も関心を寄せたのは事件後の対応で、秩序の立て直し段階にもかかわらず法の不在とも形容すべき事態に、当時大きな違和感を持ったのを覚えています。特に同テロの後のアフガニスタンへの侵攻について秩序だった社会の構想に基づいた諸判断ができたとはいい難い状況を目の当たりにしたことが、動機づけという点では一つ目に挙げられます。実際、大学に入学して当面は、この関心にしたがって国際法を軸にあれこれ調べていたのですが、なかなかこの道具立てだけでは難しいぞというところが出てきます。
それがもうひとつ目のきっかけで、その頃から「アーキテクチャ」という概念が、当時においては非常に使い勝手の良い道具立てとして広く利用されるようになってきたことがあります。物理的な環境の組成が動作主に何をアフォードするか、といった議論は当時以前から既に人口に膾炙していたかと思いますが、ローレンス・レッシグの翻訳(や、東浩紀さんが中央公論で連載していた「情報自由論」によるその紹介)を重要な契機として、本邦の法学分野にもそうした、物理的な環境への介入によって人々の判断・行動を制約するというリスクが顕著なものとして持ち込まれるようになった。つまり、アーキテクチャがあれば法が担ってきた機能の多くがより効率的に(規範への直面さえなく)代替されうるのか、そうではなくアーキテクチャは(事前の監視や事後の制裁を統制する)法に求められてきた内容的・手続的な「正しさ」をスキップするリスクを増大させるのか。後者であれば、アーキテクチャの設計・構築から運用・継続に至るどの段階について、どの主体が、どのようにコントロールするのか。こういった課題を前にしつつも、どこから手をつけたものかと分野をがらっと変えてみたり、証券実務方面からアーキテクチャ構築に携わったりと右往左往しながら法哲学に戻ってきたというのが、実際の経緯です。
– 先生方はちょうど小学生から大学生にかけて、Windows95の登場から「IT革命」、ブロードバンドやSNSの普及などを経験し、学問を志していった世代かと思います。既に上の世代が一定の基盤をつくった上に新規性を発揮していくような部分と、初期のデジタルネイティブ的な要素も入ってきた中だからこそ見える部分と両方の要素をお持ちであると推察しますが、その中で、ご自身の研究や教育が、情報と法・政策等に果たす役割はいかなるものだとお考えですか。
永石:さきほど言説上の先行世代の話をしましたが、技術的なものも上の世代の方が「技術オタク」が多く……我々はライトユーザーになりかけていく時代だと認識しています。
酒井:そうですよね。ちょうど5歳から10歳ぐらい上の世代の方のイメージです。
永石:Windows95もそうですけど、ホームページ乱立時代みたいなのもやっぱり一世代前ですし、僕らのときにはブログやるか、みたいな話になってきていた。要するに大衆化されたサービスの中にあったので、デジタルネイティブと言われると、どのネイティブなのか?というところはあるかもしれません。
ただ研究上、そうした情報技術上の変化が規制する側、規制される側の振る舞いをどう変容させ、また規制自体にどう跳ね返ってくるか、という点では必然的に取りこむ必要があることは確かです。例えば、先ほどあげた同時多発テロ後、中東諸国等からの入国者については、既に滞在している人も含めて指紋押捺や写真撮影などを強制する取り組みを始めました。安全保障目的が正当性を持つことに疑いはありませんが、ここで人を識別するために用いられる情報、特に生体情報は必ずしも関連性があるものを選り分けて用いられるとは限りません。しかし、こうした取得・蓄積の技術の進展が利用態様に否応なく跳ね返ってくることは想像に難くなく、今般のCOVID-19への対応においてもこのことはみてとれるでしょう。古典的といえば古典的ですが、例えばこうした科学的証拠としての価値を法実践上で位置付ける仕組みの中にも、「情報と法」の結びつきを見ることができるのではないでしょうか。
酒井:著作権法は技術発展と分かち難く結びついていますので 、最先端の技術やサービスと著作権の問題を研究課題として扱うことが必然的に増えます。したがって、もちろん人によりますが、他の法分野よりもそういった新しい技術やサービスに触れることを苦手としない研究者の方々が多い傾向にあるように思います。 私は特段コンピュータ技術に詳しいわけでもないですし、いわゆる文系で、技術を理解するのって難しいな、と思う側の人間ですが、幸いなことに今、情報学環にいることで、生成AIであったりメタバースであったりと、新しい技術を研究されている先生や学生の方がいらっしゃるので、色々な人に話を聞き勉強し、法的な問題を考える環境に身をおくことができているかなと思います。
最初に申し上げた通り、私の研究は写真という割と古い機械の話を取り上げていますし、古い時代の話なので、すぐに新しい技術の法解釈に結びつくものではありません。ただ生成AIの場合、機械によって作られたものである、ということの意味をもう一度考え直すような側面があって、その時に、写真が新技術として登場した時の議論がオーバーラップするように見えること があります。ですので、写真と著作権の研究をしていると人に言うと、 面白そう、みたいな反応をされ ることがあります。
– 生成AIの急速な発展・普及が社会に大きな変化をもたらそうとしています。情報に関する法・政策や法哲学・法社会学等に及ぼす影響はやはり大きいでしょうか。どのようなことが問題になると考えられますか。
酒井:もちろんインパクトは大きいと思いますが、例えば、今までと全く違う法解釈をする 、法律を一から新しくする、ということは少ないと思っています。もちろん、判例や学説においてこれまで積み上げられてきた様々な解釈を、新しい技術にどう対応させていくか、という試行錯誤は生じると思いますが、少なくとも現時点の技術状況では、法体系そのものを変更させるまでにはならないだろうと思います。
解釈の試行錯誤では、例えば、生成AIの学習・出力過程をどのように評価するか、という問題があります。著作権侵害になるためには「元の著作物に依拠して作られたこと(依拠性)」と「元の作品と問題となった作品が類似していること(類似性)」が必要ですが、AIの機械学習の過程でとある著作物が学習されているけれど、出力を指示したAさんはその著作物を知らない場合、依拠性を満たすのかという論点が生じる。また類似性も、画風の類似だけであれば類似性は否定されて著作権侵害になりませんが、Bさんの作品群と似た画風の作品を出力できるAIが登場した場合、どこまでが「画風」でどこからが著作者の創作的表現と捉えるべきなのか、という問題がありそうです。特に画像の場合、まず議論するために画像の特徴を言葉で表す必要があり、特徴の捉え方は人によっても異なるので、線引きが難しいように思われます。
もちろんこの先の状況では、法体系に影響が生じる可能性もあると思います。例えば、生成AIによって出力された生成物を著作物とするか、著作物であるとするならその作者は誰かという問題です。現在の著作権法では、著作物は人間による創作的表現であると捉えているので、AIによる生成過程に一定の人間の関与がある、少なくともそう判断できる状況がない限り、AI生成物は著作物ではないし、またAIは著作者にならない、と一般的には考えられています。しかし将来、AIが完全に自律的に作品を生み出すことができるようになった場合、そしてそれらの作品に一定の保護を認める必要があって、しかも特別法を作るのではなく著作権法で規律する必要が生じた場合には、著作権法の根本となる概念、何を著作物とするか、誰を著作者とするか、といった点に影響が生じることになり、法体系に影響が生じることもありえます。
ただ、それらの問題は生成AIに特殊な問題というわけではなく、今まで認識はされてきたけどあまり 取り上げられてこなかった論点の延長線上で検討されていくものなのか もしれません。AIが著作者になることができ るか、という論点 は、例えば、動物が著作者になれるか、というある種古典的な論点と地続きです。
また政策との関係では、AIの開発・利活用をどうしていくべきか、といったルールメイク、政策の方向性が先に生じて、それに法律が影響されるという面もあります。他方で、政策で大胆なことが決まったので、既存の法律もドラスティックに変わる、ということではなく、うまく解釈で引き受けることができないか、という試行錯誤の中で進む感じなのかなと思います。
永石:法について語る時、私を含めて法学研究者は法解釈のことを中心に考えてしまう傾向があるかと思いますが、多分、法学以外の人の中心的イメージは立法ですよね。例えば2018年の著作権法の改正では、30条の4で非享受利用(著作物を鑑賞する目的で利用しない場合)や47条の5の軽微利用(新たな情報・知見を創出するサービスの提供に付随して、著作物を軽微な形で利用する場合)のように、情報化解析、大量の情報を機械に学習させる著作物使用の特定の類型について、著作者の許諾がなく使用できるとする条文が追加されました。しかし、もちろんこの追加は政策一辺倒ゆえのものではありません。政策的に立法が走ったあと、2023年現在話題になっている生成AIについて語られるように状況が変動したかに見える中でも、解釈の中で着地点を目指すような、キャッチボール的な側面があるわけです。例えば、運用上の要求が高い部分は政策的に、あるいは立法的に割とショートピリオドでボールを投げる局面もあるかもしれませんが、その具体的な適用段階の蓄積こそが法自体を再帰的に明らかにし、さらにはその法の限界を人々に可視化し、政策を動かすフィードバックも生み出すということも、ここで話題となっている著作権分野では期待されているかもしれません。
「法」というとなにやら「中の人」があれこれ言葉をこねくり回しているように見える場面もあるかもしれませんが、どちらかといえば「中の人」という単一の主体は不在で、そこでのボール回し(時に異議や抗議といったコンフリクト)のなかで、状況変化に合わせた決断の連鎖がなされ、ルールの細部が調整されていく、というゲーム的なイメージの方がしっくりくるかもしれません。そのゲームを観戦しているギャラリー席側のガヤガヤした声も含めて「法」を動かす要因と捉えることさえできる。上で述べた「政策を動かすフィードバック」のダイナミズムもまた、法を取り巻くゲームの一部に組み込まれている、とも言い換えられるでしょう。
この点と関連しつつ話を戻しますと、生成AIのインパクトを検討する上では、テキスト、絵画、音楽などなど何をアウトプットとして出すかのみならず、どういう文化の中で培われてきたものを、どういう場面で、誰に対して出すか、という対象領域となるフィールドの違いも重要な気がしています。言い換えれば、与えるインパクトは「ジャンル」依存で様々に影響が異なりうる。例えばテキスト一つとってみても、同じ文字情報を排出するときでさえも、教育現場で生じる問題と、研究上のピアレビューが働く場面での問題、さらに速報的に目に入る情報が生み出す問題と「確からしい」情報として蓄積される際の問題等は、各々異なりうるはずです。
このように見ていくと、もともと機械的な処理になじむ文化・性格を持っているような類のものとそうでない類のものが併存する中では、法的なハードルをクリアしさえすれば事足りる、という場面は、実践的にいえばむしろ少ないかもしれません。反対から言えば、どういう形でそうしたフィールドの重畳性が相互に影響を与え合っているのかを正確に把握しながら、それでもなお強制力を伴う法がいかなる形で介入するか(しないか)を検討するための概念や道具立てを提供することが、「情報と法」を研究・教育する私たちには課されているものと受け止めています。
(後編に続く)
企画:学環ウェブ&ニューズレター編集部
インタビュー:畑田裕二(助教)、山内隆治(学術専門員)、柳志旼(博士課程)
インタビュー&構成:神谷説子(特任助教)
英語抄訳:デイビッド・ビュースト(特任専門員)
主担当教員Associated Faculty Members
准教授
酒井 麻千子
- 社会情報学コース
Associate Professor
SAKAI, Machiko
- Socio-information and communication studies course