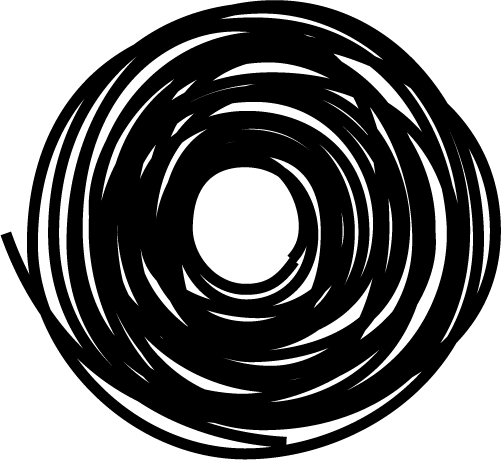June 27, 2025
【教員インタビュー】筧 康明教授 (後編)Faculty Interview: Professor Yasuaki Kakehi (Part2)
先端表現情報学コース、文化・人間情報学コース、ITASIAの3つのコースでマテリアル・エクスペリエンス・デザインのご研究をする筧 康明先生のインタビューです。
本インタビュー記事は、前編と後編に分けて掲載します。前編ではご研究テーマとそれに至った背景について伺いました。後編では、筧先生が研究の場で大切にされている視点・アプローチと学府・学生へのメッセージを伺いました。(前編)
The following interview was conducted with Professor Yasuaki Kakehi , whose field of research is Material-Driven Experience Design. Part 1 deals with his research topic and the background leading to it. Part 2 focuses on the values and perspectives he adopts in his research, as well as his message for the graduate school and students.(Part1)
日本語は抄訳に続く(Japanese interview text follows English summary)
Part 2.
Prof. Kakehi has been involved in a number of university-industry joint ventures, including a year-long project with the Sony Group exploring ways to combat bias using technology. This brought together people working on media art and design with those in the humanities and social sciences as well as personnel from Sony. Through such projects, Prof. Kakehi seeks to break down barriers that still stand in the way of broader collaboration both within the academy and beyond.
Prof. Kakehi also aims to promote interaction and collaboration among the diverse students in his laboratory, even while they each pursue their own unique projects. Roughly half of his current students come from art college backgrounds with the remainder coming from engineering schools. Painters, craftspeople and architects number among the former while the latter include mechanical engineers, electrical engineers and material scientists. They come to the laboratory with different prior experience and represent different age groups and nationalities. All members of the laboratory, including Prof. Kakehi himself, therefore have much to learn from each other.
Among the qualities he seeks in students, Prof. Kakehi cites a desire to create things, an attention to detail, and a willingness to work alone or in collaboration with others. He hopes that the diverse and interactive nature of his laboratory will foster new abilities in all those who participate.
―― 昨年度、学環ウェブにて筧先生が主導されている「社会連携講座」の記事を多くお見かけしました。こちらについて教えていただけますか。
一つは、ソニーグループと進めている「越境的未来共創社会連携講座」で、これまでの学際の枠組みを超えて、これまで繋がり切れていないところを繋げたいというモチベーションでやっています。2023年の12月に始まって、今ほぼ1年経ったところなんです。去年は「Tech Bias テクノロジーはバイアスを解決出来るのか?」というテーマで、学環学府の中の人文社会学系の皆さん、理工系とか僕らのようなデザインとかアートをやっている皆さん、そしてソニー内の多様な部署から志願した方々がそれぞれが3分の1ぐらいに関わるようなチームを4チーム作り、10ヶ月間ぐらいずっと議論とモノ作りを回しながら、いわゆるテクノロジーそのものが持つバイアスを明らかにしたり、解決に挑戦していくような、実践プロジェクトをやってきました。
これまで文理融合や産学連携やっぱり心地良いところでのコラボレーションしか起こってなくて、それを私たちは学際のように見ていたけど、実はもっと振り幅の広いところでコラボレーションを作っていくことによって、お互いにとってさらに面白いこと新しいことができるんじゃないかっていうことを思ってて、そういう取り組みを作ってみたんです。
そうすると、やっぱりすごく面白くて、批評的な眼差しと、創造性、そして共創性っていうのを併せ持つような取り組み、あるいは人材をどう作っていけるかという取り組み方っていうまだまだあって、それを阻んでいるのは何かわかんないんですけど、あえてそこを取り外すようなフレームを作ることによって生まれる可能性があると思っています。
―― 先生の研究室の学生さんたちは、実に様々なジャンルの研究に取り組まれています。皆さんそれぞれが、様々なテーマを持ち込んで、研究室に集まって来られるのでしょうか?
ラボとして、プロジェクト的に進めているものがあって、希望があればそこに参加してもらうというようなこともありますし、自分でやりたいテーマを持ってきて、それをラボで何かしら形にすべく、実践している人もいます。でも、家で一人で出来てしまうような事に取り組むならば、せっかく大学のラボという中で活動するのですから、できるだけ周りの、自分とは少し異なることをしている人とか考えている人とコラボレーションするようにした方が面白いよ、という話は良くしています。最終的には修士論文や博士論文で、責任を持つという事は必要ですが、その過程においてはさまざまな人とコラボレーションができるようにと思っています。今は、学生の半分ぐらいは美大や藝大から、残りの半分は、工学的、サイエンティフィックなところから来ています。その中には画家、工芸家、建築家の人もいれば、デザインの仕事をしている人もいます。工学の方面では、機械工学、電気工学、材料工学。いろんな人がここに来たら何かちょっと違う新しいことができるだろうという期待感のもとに来ています。みんなの関心をみんなで議論して育てていくようなことをやっているので、これは学際の極みとも言える面白い状況です。国籍、年齢層も多様でになってきていて、すでにプロとして活躍している人も、宿り木のように、ここに来ています。一方的に僕が何かを教えるという関係ではなくて、それこそお互いに学び合うそういう場所になってきているという感じですね。
―― 研究室のいろんな学生さんをご指導される上で、大切にされていることはありますか。
一つはやはり対話です。一緒になってアイディアから作っていくということをやっているので、対話はすごく大事です。学生同士の横の繋がりはもちろんそうですし、僕自身が、作るということを傍でずっとやり続けることは結構大事だと思っています。フィードバックの壁としての存在だけでなく、一緒になって作る、考えることを大事にしています。こういう領域は、僕自身まだ見たことのないものをどうやって作っていくかという事なので。僕だけが答えを知っていて、みんなが知らないことを教えてあげるということではありません。時には同じ方向を向いて走っていかないといけないし、時には向かい合って話し合うことが必要で、その視点の置き方が、腕の見せどころなんだと思います。先生として、そしてコラボレーターとしてですね。
ーー どういう学生に来てほしいとお考えですか?
作るということに関して関心があるというか、こだわりがあるというところは、すごく大事だなと思っていて、ただ一人で全てを作り出すというか、さきほどお話ししたように、いろんな人と繋がりながら作り出すことができるということに長けているのか。あるいは、ここでその能力を開花させる可能性、そこに対しての抵抗感がないということ。そこはすごく大事かなというふうに思ってます。
コラボレーションの中で人自体、職能自体が変化していってオーバーラップしていって、時には違う人の視点で物事を見るとかっていうことが必要になってくるということでいうと、いわゆる専門性がしっかりと確立されていて、その間のインターフェースのところで何かものを作ろうという、その従来タイプの協力関係ではないっていう感じですかね。もっと人も含めて入り交じりながら、ひと自体も変容していきながら、有機的にものを作って、その果てに何か新しい職能を持った人が立ち上がってくるといいなという感覚でやっています。
企画:学環ウェブ&ニューズレター編集部
取材:開沼博(准教授)・畑田裕二(助教)・山内隆治(学術専門員)・原田真喜子(特任助教)・柳志旼(博士課程・編集部)
構成:山内隆治(学術専門員)・原田真喜子(特任助教)
英語抄訳:デービッド・ビュースト(特任専門員)
(取材日:2025年1月6日)