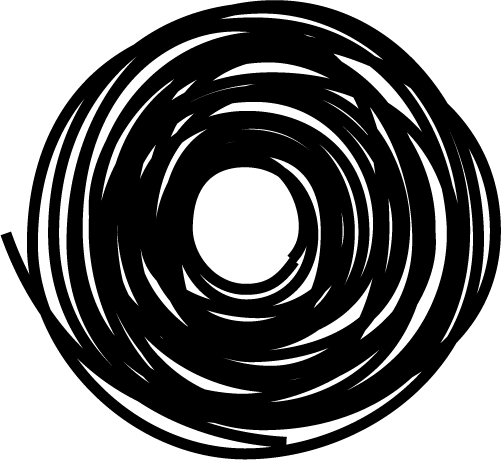October 28, 2024
助教のお仕事 ー 学府所属の助教へのアンケート結果よりAssistant Professor Jobs - Results of a survey of assistant professors affiliated with III
(本文は抄訳に続く)
A survey was conducted with five assistant professors from the Interfaculty Initiative in Information Studies to explore their experiences and perspectives. Their research topics range from AI-supported communication and science education politics to sociological studies on mobility, VR-based self-actualization, and genome data analysis. In addition to research, they handle diverse responsibilities like teaching, university management, and student supervision, making their schedules busy.
The time dedicated to research varies, and many have adopted strategies to balance research and administrative duties. Their reasons for pursuing an academic career include the appeal of university administration, interacting with diverse researchers, and the independence that comes with being in academia.
Regarding private time, some professors try to separate work and life, while others view research as an integral part of their lifestyle. One key reward is their engagement with students, guiding their growth and contributing to the development of research.
Looking to the future, many assistant professors aim to continue their research in tenured positions and further deepen their research projects. Some have unique visions, seeking to pursue academic activities centered around shared “interesting” ideas with peers rather than focusing on competition or responsibilities. Others have ambitions to write books aimed at a general audience, expressing a desire to share their research findings with a wider public. The directions they pursue are diverse.
These assistant professors value deepening their research while contributing to society and their students, and their activities are expected to have a significant impact on the advancement of academia and their own career development.
助教として働くことはどのような経験なのでしょうか。助教という職務は、大学における教育や研究の要となる重要な役割を担っていますが、その仕事の実態はなかなか明らかになっていません。今回、編集部では情報学環に所属する助教の皆さんにアンケートを実施し、その仕事や考えについて伺いました。
(アンケートを行った時期:2024年7月28日-9月20日)
回答を寄せてくださった助教:5名(アルファベット順)
Chi-Lan Yang(ヤン チーラン)https://www.chilanyang.space/
Duim Huh(ホ ドゥイム)
Eunbyul Ahn(安 ウンビョル)
畑田 裕二 https://yunolv3.work/
Seohyun Lee(イ ソヒョン)
Q1:現在取り組んでいる研究テーマについて教えてください。
現在(2024年9月9日時点)、情報学環の教員は60名(兼務教員を除く)で、助教は9名(特任を除く)います。
本企画では、ヒューマンコンピュータインタラクションや人工知能を使ったコミュニケーション支援(Yang先生)、科学技術社会論に基づく科学教育の政治的側面(Huh先生)、現代社会のさまざまな移動の実践とそれをめぐる表現に関しての社会学的研究(安先生)、VRを用いて「なりたい自分」を実現する方法論の研究(畑田先生)、自然言語処理技術を用いたゲノムデータの解析(Lee先生)、文系から理系までさまざまな領域でご活躍されている5名の助教からご回答をいただきました。
Q2:日々の主なお仕事の内容(教育・研究・大学運営・その他)について教えてください
助教の業務は、教育、研究、大学運営、その他さまざまな分野に広がっています。今回のアンケートでは、具体的なお仕事の内容を伺うことができました。
教育面では、学生やインターンの指導、講義の準備に4割~5割の時間を費やされているという先生がいらっしゃいました。非常勤講師として、東京大学以外の複数の大学で教鞭を取られている先生もいました。研究室では、学生と一緒に研究アイディアを考えたり、進捗確認、論文執筆のサポートをされているそうです。
また、国際寮での学生相談に携わっている助教もいました。年齢が近く、他国で研究者として働く先輩が相談に乗ってくれる環境があることは、留学生にとってとても心強いと思いました。
研究面では、勉強・調査(データ収集、資料収集、先行研究調査、参与観察の遂行など)、論文執筆・投稿、学会発表といった学生と同じプロセスのものに加えて、研究プロジェクト(筆頭のもの、学生との共同、先生が代表を務めるものの一環など)の推進、研究費確保、共同研究者との議論といったことをされているようです。研究は教育活動と不可分に結びついている側面もあり、学生さんと一緒に研究プロジェクトを進めるのが役割の一つとのコメントもありました。
大学運営においては、会議を中心に、各種シンポジウムやホームカミングデーの企画・運営や入試業務のサポートなどがあり、要する時間は勤務時間のおおよそ2割ぐらいという声もありました。ですが、職場での役割やスケジュールを最優先し、その都度しっかりと仕事に備える必要があるため、精神的には2~3割とは言い難い部分もあるかもしれないとのことです。
社会的活動として、学会の運営業務や、取材対応、種々のイベントにおける講演、勉強会講師などもされているそうです。
Q3:自身の研究時間として、どのくらいのお時間を割いていますか?また、そのお時間を捻出するための工夫があれば教えてください。
このアンケートに回答された5名のうち、研究に当てる時間は、3割~5割と、助教の中でも幅がありました。毎日少なくとも2時間を研究に充てることを意識していて、仕事の合間にメール処理の時間を区切り業務効率を向上させる工夫や、研究に優先順位を付けることを最も重要とし、メールが溜まらないように、メールの量を最小限に抑えるよう努められているという回答がありました。
他にも、計画性を重んじ、年初に立てた研究目標達成に向けて行動されている先生や、他の先生方と協力して働きながら、自分の研究を進めるというバランス感覚を持つことが大切との声もありました。助教の先生たちは、ご自身の研究時間を確保するためにさまざまな工夫をされていることが明らかになりました。
一方で、ときには数時間の研究没頭時間を確保するのが難しいと感じる先生もいました。静かな、他に何も考える必要のない環境で研究したいとされつつ、日々の人との対話によって、研究が醸成されると感じているそうです。
Q4:大学助教としてのキャリアを選んだ背景を教えてください
この問いへの回答では、研究を続けたいという強い希望が共通していることがわかりました。ところで、大学院修了後に研究を続けるというキャリアはどのようなものがあるでしょうか。
学術機関の研究職について、具体的に記してくださった回答がありましたので、一部紹介したいと思います。
⓪博士号取得後すぐにテニュアトラックの大学教員になるのは非常に珍しく、よほど素晴らしい実績と運が必要、①ポスドク研究員(学振のPDなど)、②助教(ほとんどが任期付き)、③プロジェクトベースの助教や研究員、④非常勤講師として実績を積みながら公募に応募する
学術機関以外の選択肢としては、企業研究者や独立研究者など多様な形態がありますが、ここでは割愛します。
さて、このような選択肢から学術機関の研究職である助教を選んだ理由としては、大学の運営への関心(Lee先生)や、多様な分野の研究者と交流できる環境への魅力(Huh先生)、大学所属ならではの経験と独立性という独特なポジションへの魅力(安先生)、一緒に対話し思考を深めたいと思える師や友人がいるから(畑田先生) といった声がありました。
Q5:「研究活動以外のプライベートの時間」をお持ちですか?
この質問についての助教の先生の回答は大きく二分したようです。一つ目は、週末に意識的に仕事を離れる環境を作ったり、研究活動以外のプライベート時間を確保することを大切にされている先生方。Huh先生は、映画鑑賞や読書(研究に直接関係のない本)に親しみ、Lee先生は編み物などの趣味を楽しむなどでリフレッシュしているそうです。
二つ目は、生活している間にも研究のアイディアを得たり、研究するというのもライフスタイルの一つだと思うのでプライベートと仕事が分けられるとは考えていない(An先生)、研究が趣味であるためプライベートと切り分けられない(畑田先生)という先生方です。
とはいえ、完全に一致させることは難しいようで、「研究に関する考えや実績へのプレッシャーを完全にオフにできる時間があれば」、「本の読めなさを忙しさのバロメーターとして意識し、切り離す努力はしたいと思っている」とのことです。
Q6:助教としての活動で特にやりがいを感じる点は何ですか?
「新しいアイデアやスキルを毎日学び続けられること」「やる気のある学生や共同研究者との仕事」「異なる分野の知識を学び、様々な人と出会えること」などの回答をいただきましたが、最も多かったのは学生との関わりに関するコメントでした。
教育部の授業で、成績に縛られない自発的な学びと学生の純粋な情熱を感じ、その制度の素晴らしさと受講してくれた学生への感謝を綴ってくださった先生や、学生の相談に応じるときに、彼らの将来の自己実現に資するような機会を提供できた時が一番嬉しいという先生もいました。学生の研究指導を補助する中で、さらにやりがいを感じる場面が増えることを期待したいというコメントもありました。
他にも、学際情報学府の修了生なので、その運営の舞台裏を知ることやさまざまな決定事項に関わることができるという点が魅力的であるという声もありました。
Q7:「将来の目標」や「ビジョン」または「理想の生き方」についてについて教えてください
助教の先生方の将来の目標は、研究を続け、質を上げると共に、科学の発展と社会に貢献することを意識されたものでした。
研究に関する声には、2タイプのビジョンと一つの理想を語るコメントがありました。前者の一つ目は任期のないポジションについて少しゆったりと研究を進めたいというもの、二つ目は研究プロジェクトを繋げ、突き詰めて行きたいというものでした。そして最後の一つは、競争でも任務でもなく、仲間と共に「面白い」を起点に実現するブリコラージュ的な学術活動に関心を持っているというものでした。
また、「書く」お仕事に関心がある先生が2名いました。Yang先生は、ご自身の研究について一般向けの本を執筆するという目標があるそうです。安先生は、母国と日本で「書く」仕事に取り組み続けたいそうです。同じ「書く」作業でも、内容やモード(言語、トーン、発表する雑誌、読者層、考え方のアプローチなど)が異なるため、並行するのがなかなか難しいとのことです。
Q8:そのほか、ユニークな立場、価値規範をお持ちでしたら教えてください
このアンケートに回答された先生の半数は「特にない」という回答でした。一方、『この年齢にはこれをしなければならない』という固定観念から比較的自由であることが、ユニークな生き方であり、ご自身は既にユニークな生き方をしていると思うというお考えを伺うことができました。
まとめ
助教としての仕事は多岐にわたり、多忙な毎日の中でも研究と教育、大学運営、プライベートのバランスを取りながら取り組まれている様子を伺えました。助教の仕事が以前よりもイメージしやすくなったのではないでしょうか。
それぞれの助教が、ご自身の研究を深め、社会や学生に貢献するための努力を続けており、将来的には学術の発展とともに自らのキャリアを形成していくことが期待されます。
ご多忙の中、アンケートにご回答いただいた助教の皆さまに深く感謝を申し上げると共に、今後ますますのご活躍をお祈りしております。
企画:学環ウェブ&ニューズレター編集部
構成・抄訳:原田真喜子(特任助教・編集部)&畑田 裕二(助教・編集部) &柳志旼(博士課程・編集部)
英語校正:デイビッド・ビュースト(特別専門員)