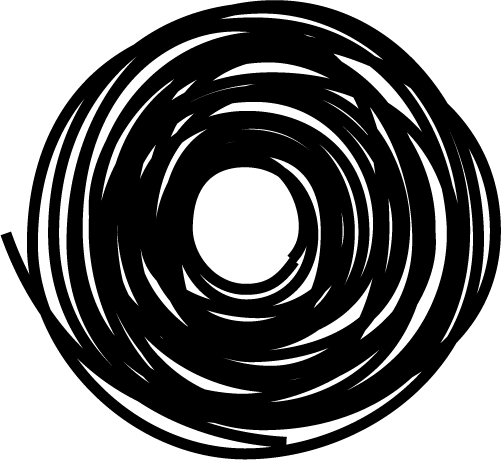May 19, 2025
令和6年度大学院学際情報学府 学位記伝達式GSII Degree Conferral Ceremony AY2024
3月24日、福武ラーニングシアターにて学際情報学府の学位記伝達式が行われ、修士課程修了生100名、博士課程修了生13名に学位記が伝達されました。厳かな雰囲気の中、司会から修了生たちの名前が読み上げられると、修了生は一人ずつ演台の前へと進み、目黒学府長の手から学位記を受け取りました。また、学際情報学府の総代として全学の学位記授与式に出席した白木美幸さん(修士、写真左)と山田渉さん(博士、写真右)の紹介も行われました。修了生への学位記伝達が終わると、目黒学府長より祝辞が贈られました。
閉会の後は、研究室のメンバーが集まって祝花の前で記念写真を撮ったり、修了生がお世話になった教員と歓談したりと、和やかに節目を祝い合う様子が印象的でした。
【学府長賞】
村本 剛毅(先端表現情報学コース)
「Alternative See-through: ビデオシースルーHMDを基盤とした代替的視覚の設計論」
【専攻長賞】
〈社会情報学コース〉
白木 美幸「Intimate Affairs of the Embodied Feminine Ideal: Disentangling Material-Discursive Fashion Practices in Post-war Japan (「親密な」女性性の身体化を紐解く: 戦後日本の物質-言説的なファッション実践の社会学的考察)」
〈文化・人間情報学コース〉
毛 雲帆「動物化から始まるポストヒューマンの<身体> ―中国のファーリー・ファンダムの分析を通して―」
〈総合分析情報学コース〉
時田 聡実「身体動作の効率的な学習と多様な表現力を支援するXRシステムの提案」
〈アジア情報学コース (ITASIA program)〉
SUGA Tomoka「Femtech Entrepreneurship in Japan: Defining “Women’s Work” in a Newly Emerging Technology Field」
〈生物統計情報学コース〉
澤田 航太「”Dynamic borrowing with a bias tolerance cap in augmented randomized controlled trials”(バイアスの許容上限を与えた外部対照の動的利用法に関する研究)」
【コース長賞】
〈社会情報学コース〉
佐久間 弘明「生成AIリスク言説における決定と責任──フレーミング分析による観察図式の解明」
清水 将也「「丸サ進行」の時代 ―ポピュラー音楽のマルチモダリティ分析―」
尚 倩玉 「『人⺠日報』サブアカウントの言説分析 ―「侠客島」の「コロナ」報道を事例に―」
冨田 脩史「通信データ保存法制の在り方について ―通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティに係る課題を中心として―」
中里 朋楓「非常時のデジタル空間における偽情報・誤情報の流通」
福井 桃子「緊急時の命を守るための説得——走行中の車内で旅客に適切な行動を促す車内放送に関する研究」
〈文化・人間情報学コース〉
入澤 充「証言的対話に基づいたアライの教育プログラムの開発」
高 澤雄「アクティブ語彙学習の遠隔・近時記憶についての研究 ―高校生のオンライン学習における辞書引きにフォーカスして」
曹 好「“Pieces of Peace” -Workshops and toolkit design for reconstructing peace storytelling from war photographs(「平和のかけら」-戦争写真を用いた平和ストーリーの再構築のためのワークショップおよびツールキットの設計)」
〈先端表現情報学コース〉
伊藤 映美「効果的な防災教育プログラムの構築と評価方法の検討」
加藤 宗一郎「地域特性を踏まえた効果的な災害情報発信のための地域メディア向け災害放送業務支援システムの提案」
中條 麟太郎「テキストコミュニケーションにおける書体が信頼性・支配性の印象と意思決定に与える影響」
程 柏朗「Designing Product Endings through Degradation: A Methodology for Sustainable Design (ものの終わりを劣化からデザインする:サステナブルデザインのための方法論)」
中根 葵「手繋ぎ可能な分布触覚五指ハンドによる状態認識と適応行動の実現」
森村 太一「床・壁・天井の間を移行する群ロボットの研究」
〈総合分析情報学コース〉
賴 欣妤「Investigating Transmission Delay’s Role in Conditions for Inter-brain Synchronization in Remote Communication(遠隔コミュニケーションにおける脳間同期の条件と通信遅延の影響に関する研究)」
今村 翔太「会話から推定される関心に合わせた学術情報探索・要約システム」
松永 惟月「分散環境におけるデータ主権に基づいた共有データの動的検索を行う連邦型RAG」
〈アジア情報学コース (ITASIA program)〉
XU Yang「Violence, What Violence? Exploring Aggression in K-pop Boy Group Music Videos and Its Reception by Young Chinese Female Fans」
〈生物統計情報学コース〉
吉野 瑠里夏「進行性大腸がん患者における遺伝子変異情報を用いた術後再発リスクの予測モデル構築」
記事:学務チーム
On March 24th, a ceremony was held in the Fukutake Learning Theater for the presentation of degree certificates to graduates of the GSII. In a solemn atmosphere, the graduates walked to the podium one-by-one to receive the certificates presented to them personally by Dean Meguro. There were also introductions for the two students, SHIRAKI Miyuki (M.A., photo on the left) and YAMADA Wataru (Ph.D., photo on the right), who represented the GSII at the university-wide graduation ceremony.
After the ceremony, commemorative photographs were taken with colleagues in front of the floral display and graduates enjoyed conversations with their former professors in celebration of the occasion.
【The Dean Award】
MURAMOTO Goki(Emerging design and informatics course)
「Alternative See-through: ビデオシースルーHMDを基盤とした代替的視覚の設計論」
【The Head of Department Award】
〈Socio-information and communication studies course〉
SHIRAKI Miyuki「Intimate Affairs of the Embodied Feminine Ideal: Disentangling Material-Discursive Fashion Practices in Post-war Japan (「親密な」女性性の身体化を紐解く: 戦後日本の物質-言説的なファッション実践の社会学的考察)」
〈Cultural and human information studies course〉
MAO Yunfan「動物化から始まるポストヒューマンの<身体> ―中国のファーリー・ファンダムの分析を通して―」
〈Applied computer science course〉
TOKIDA Satomi「身体動作の効率的な学習と多様な表現力を支援するXRシステムの提案」
〈Information, Technology, and Society in Asia (ITASIA)〉
SUGA Tomoka「Femtech Entrepreneurship in Japan: Defining “Women’s Work” in a Newly Emerging Technology Field」
〈Biostatistics and bioinformatics course〉
SAWADA Kota「”Dynamic borrowing with a bias tolerance cap in augmented randomized controlled trials”(バイアスの許容上限を与えた外部対照の動的利用法に関する研究)」
【The Head of Course Award】
〈Socio-information and communication studies course〉
SAKUMA Hiroaki「生成AIリスク言説における決定と責任──フレーミング分析による観察図式の解明」
SHIMIZU Masaya「「丸サ進行」の時代 ―ポピュラー音楽のマルチモダリティ分析―」
SHANG Qianyu「『人⺠日報』サブアカウントの言説分析 ―「侠客島」の「コロナ」報道を事例に―」
TOMITA Naofumi「通信データ保存法制の在り方について ―通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティに係る課題を中心として―」
NAKAZATO Tomoka「非常時のデジタル空間における偽情報・誤情報の流通」
FUKUI Momoko「緊急時の命を守るための説得——走行中の車内で旅客に適切な行動を促す車内放送に関する研究」
〈Cultural and human information studies course〉
IRISAWA Mitsuru「証言的対話に基づいたアライの教育プログラムの開発」
GAO Zexiong「アクティブ語彙学習の遠隔・近時記憶についての研究 ―高校生のオンライン学習における辞書引きにフォーカスして」
CAO Hao「“Pieces of Peace” -Workshops and toolkit design for reconstructing peace storytelling from war photographs(「平和のかけら」-戦争写真を用いた平和ストーリーの再構築のためのワークショップおよびツールキットの設計)」
〈Emerging design and informatics course〉
ITO Eimi「効果的な防災教育プログラムの構築と評価方法の検討」
KATO Soichiro「地域特性を踏まえた効果的な災害情報発信のための地域メディア向け災害放送業務支援システムの提案」
CHUJO Rintaro「テキストコミュニケーションにおける書体が信頼性・支配性の印象と意思決定に与える影響」
CHENG Bailang「Designing Product Endings through Degradation: A Methodology for Sustainable Design (ものの終わりを劣化からデザインする:サステナブルデザインのための方法論)」
NAKANE Aoi「手繋ぎ可能な分布触覚五指ハンドによる状態認識と適応行動の実現」
MORIMURA Taichi「床・壁・天井の間を移行する群ロボットの研究」
〈Applied computer science course〉
LAI Sin-Yu「Investigating Transmission Delay’s Role in Conditions for Inter-brain Synchronization in Remote Communication(遠隔コミュニケーションにおける脳間同期の条件と通信遅延の影響に関する研究)」
IMAMURA Shota「会話から推定される関心に合わせた学術情報探索・要約システム」
MATSUNAGA Itsuki「分散環境におけるデータ主権に基づいた共有データの動的検索を行う連邦型RAG」
〈Information, Technology, and Society in Asia (ITASIA)〉
XU Yang「Violence, What Violence? Exploring Aggression in K-pop Boy Group Music Videos and Its Reception by Young Chinese Female Fans」
〈Biostatistics and bioinformatics course〉
YOSHINO Rurika「進行性大腸がん患者における遺伝子変異情報を用いた術後再発リスクの予測モデル構築」
Text: Academic affairs division
English proofreading: David Buist (Project Senior Specialist)