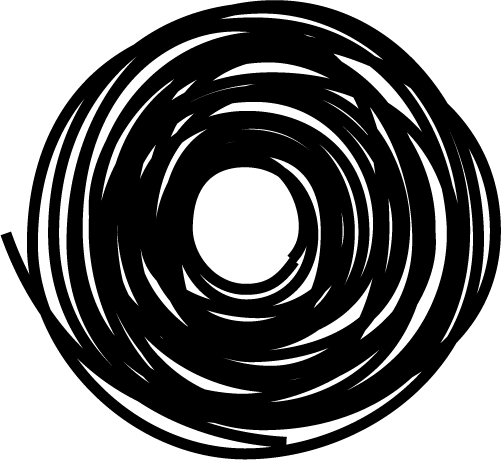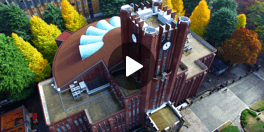September 27, 2019
【教員インタビュー】菅 豊 教授(後編)Interview with Professor SUGA, Yutaka (Part2)
フィールドに参加する民俗学、文化の担い手として文化を記述する
菅 豊 教授 (後編)
東洋文化研究所から流動教員として来られた菅先生に、闘牛(牛の角突き)と錦鯉をめぐる現在の研究とその手法について伺いました。
Folklore Engaged in the Field: Describing Culture from the Standpoint of a Culture Bearer
An Interview with Prof. SUGA, Yutaka (Part 2)
Professor Suga has come to see participation as an important part of his research methodology. Especially after experiencing the earthquake disaster of 2004 in Niigata, he felt that he could no longer simply observe but had to become more directly involved. Besides taking an advisory role, he has also increasingly found himself to be a bearer of the cultural practices he studies. His work is thus part of a larger movement for participatory research, known in the US as “public folklore”, “public anthropology” or “public history”. Avoiding the pitfalls of both total detachment and problem-identifying interventionism, he seeks to play an intermediary role between local communities and central authorities. Regarding the precarious position of folklore studies in the academy, Professor Suga notes the existence of researchers with similar concerns in other fields of study, notably sociology, anthropology and history, and expresses enthusiasm for interdisciplinary exchange.
(インタビュー前編はこちらからご覧ください)
— 研究対象に「参加する」ということをされています。
そうですね、私自身も文化の担い手になっていくというのがひとつの手法です。錦鯉についても全日本錦鯉振興会というところの名誉顧問をしていて、実は錦鯉の審査もやっています。先ほど「美とは何か」って語りましたけど…、いまだに分からなくて難しい(笑)ただ研究手法ということでいうと、私はもともとコミットメントとか、エンゲージメントを積極的にやろうと思うような、実践的な人間ではないんです。非常にベーシックに、文化とは何か、それが面白いから調べるという、知的好奇心だけで研究をしていました。
ただ、闘牛をやり始めて2004年に新潟県中越地震があって、フィールドが被災地になりました。多くの仲間たちの牛が死ぬだけでなく、家財も全部破壊されて、友人の息子さんたちも亡くなりました。そういうものを目の当たりにした時に、見るだけではいられなくなったのがこのフィールドだったんです。見るだけ聞くだけだと、なんだか場違いのような…私は何をしているんだろうっていう。そこで何かの役に立とうと思ったわけではないんだけれど、手伝いなどをやり始めていくなかで、この文化というものの担い手に自然となってしまった。それが本当のところです。
ただ、こうした関わりを持つなかでアメリカに行っていた時期があって、そこで「Public」が頭についた研究分野に興味を持ちました。私の場合には、Public FolkloreとPublic Historyに特に関心を持って調べました。これらは、Public Anthropologyも含めて全てエンゲージメントをベースに、かつては「Applied(応用)」と呼ばれていた研究分野を「Public」に置き換えるかたちでもう一回とらえ直そう、という動きです。それが私なりのやり方で、2004年以降に始まってしまった。
— 「エンゲージメント」にも、さまざまなものがあると思います。
一番スタティックなのが、フィールドワークで単に調べようっていう私の最初の姿勢ですよね。それは別にその地域に関与しようなんて意思はない。もう一端にあるのは、最初からその地域を変えよう、助けようなんて思っているあり方ですよね。極端な話、何の問題もないところに専門家としてやってきて「何か問題はありませんか?」みたいな、問題の掘り起こしをするような世界というのはある。自分たちで問題を起こしてしまうような。ふつうは、その中間形態でさまざまなことが起こるわけですが。
私も現地のさまざまなことにコミットはしていきますが、ただそこで自分から何かを売り込んでいくことはしません。これをやってみませんか?とか、こうすれば村が豊かになりますよ、といったようなね。一度だけあったのは、動物愛護法の改正のときに「これはまずいよ」とは言いました。環境省での議論に闘牛が取り上げられていて、そういうことは地元の人は知らないから。そうしたら、「なんでだ?おい、どうすんだ?!」って私に怒り出すので「いや、違う、俺が言ってるんじゃない!」って言い返しましたけど(笑)大きな問題が起こったときにそうした情報を伝えるとか、日頃のことでも聞かれればアドバイスをするとか、地域の人たちの知恵と能力が高まるなら、そこの媒介者にはなろうと思っています。フィールドワークをしていると、オンとオフがある。フィールドにいくとオン、帰ってくるとオフ。でも、オンとオフの区別がなくなってくる研究の場っていうのも、ひとつくらいはあってもいいと思っています。
— 学際的に考える姿勢について、ご意見を聞かせてください。
多分、民俗学というのはディシプリンのなかで一番弱くて、数10年後には消える運命にある。ある時代の産物なんです。近代に起こって、その時代が変わると必要性を失って消えていく。そのベースには、「野の学問」という思想が埋め込まれています。要するに、この学問は野から起こったんです。一般の人がやり始めて、それをなぜか誰かがアカデミズムに取り込もうとして、ちょっと失敗しているというのが現状です。
私はその思想としての「野の学問」に魅力を見出していますが、実際に研究をする際には、社会学、歴史学、文化人類学のなかで、同じようなことをやっている人たちがいるわけなので、その人たちの研究を受け入れ、さらにそういう人たちに対して発信していくのは当たり前のことなんです。色んな背景をもつ研究者と交わるのは、大事という以上にあたりまえなんですね。私が昨日でた研究会はPublic Historyに関する研究会で、民俗学者は私1人でした。とてもアウェイ感がありましたけど、そうした場で発言できることは重要だし、また学べることもたくさんあると思っています。
企画:ウェブサイト&ニューズレター編集部
聞き手:鳥海希世子(特任助教)
写真:鈴木麻記(特任研究員)
文章構成・英文要約:潘夢斐(博士課程)
英文要約・校正:デイビッド・ビュースト(特任専門員)
主担当教員Associated Faculty Members
教授
非公開: 菅 豊
Professor