教授
苗村 健
Professor
NAEMURA, Takeshi
- 先端表現情報学コース
- 情報学環教育部
研究テーマ
- 現実拡張・対話設計・創造支援
- 区分:
- 学環所属(基幹・流動教員)
- Emerging design and informatics course
- Undergraduate research student program
Research Theme
- Augmented Reality, Interaction Design and Creativity Support
- Position:
- III Faculty (Core & Mobile)
- 略歴
博士(工学)(東京大学)
1969年 生まれ
1992年 東京大学工学部 電子工学科 卒業
1997年 東京大学大学院 工学系研究科 電子工学専攻 博士課程修了、博士(工学)
1997年 米国・スタンフォード大学 客員助教授(日本学術振興会海外特別研究員)
2002年 東京大学大学院 情報学環 助教授
2006年 東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授(現・准教授)
2013年 東京大学大学院 情報学環 教授
- 主要業績
詳細な業績は苗村健研究室(Publication)をご覧ください。
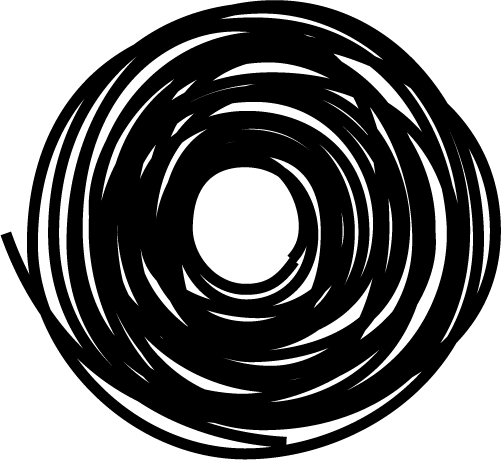


■研究テーマとポリシー
苗村研究室では,物理×情報×人間の創発的な連鎖を促す情報メデ
■現実拡張・バーチャルリアリティ
多人数が集う場における拡張現実感(AR)・バーチャルリアリテ
(1) 実物体と映像を混在させる空中結像光学系(ReQTable, AIR-range, ViPlate, GoThro, EnchanTable,HoVerTable PONG,MARIO)
(2) 映像に「情報を宿す」不可視情報重畳インタフェース(LCD 色変調, 可視光通信プロジェクタ PVLC)
(3) プロジェクタ光によるロバストな機械群制御(NavigaTor
(4) メタバースにおける HMD ユーザの支援(視線誘導・多人数鑑賞補助・酔いの低減)
■対話設計・インタラクションデザイン
さまざまな場面における円滑なコミュニケーションのために,人々
(1) 多人数会話と個人対話を切換えるオンライン音声ツール・テキスト
(2) グループワークにおける創発支援(なるほどボタン,SHelec
(3) 来館者とミュージアムを結ぶコミュニケーション支援(Peafl
(4) 筆記作業や学習を促すインタラクションデザイン(EchoShe
■創造支援・デジタルファブリケーション
中山未来ファクトリー, みんなの首里城デジタル復元プロジェクトなどの創造的なプロジェ
(1) 3D プリンタを活用した機能の創出(corobos, 3D Printing Firm Inflatables, PneuModule)
(2) 機能性素材を活かした紙面インタフェース(Inkantator
(3) ポスターデザイン・ショートビデオ制作のための支援ツール
(4) 映像の誇張表現(E-IMPACT/マンガパース)
■学生諸君へのメッセージ
東京大学総長賞・情報理工学系研究科長賞・情報学環長賞・工学部