准教授
森 洋久
Associate Professor
MORI, Hirohisa

- 総合分析情報学コース
研究テーマ
- 制御システムと博物館工学
- 区分:
- 学内兼担・課程担当教員
- Applied computer science course
Research Theme
- Control System and Museum Engineering
- Position:
- Affiliated Faculty
- 略歴
1996年3月31日 東京大学 大学院理学系研究科 情報科学専攻 博士課程 退学
1996年4月1日〜1999年9月30日 東京大学総合研究資料館 助手
1999年10月1日〜2005年9月30日 国際日本文化研究センター 文化資料研究企画室 助教授
2005年10月1日〜2009年7月31日 大阪市立大学大学院 文学研究科 助教授
2009年8月1日〜2017年3月31日 国際日本文化研究センター 文化資料研究企画室 准教授
2017年4月1日〜 現在 東京大学総合研究博物館 准教授
- Biography
1996 Mar.31., the University of Tokyo, Graduate School of Science, Drop Doctoral source.
1996 Apr.1. – 1999 Sep. 30., the University of Tokyo, the University Museum, Assistant Prof.
1999 Oct. 1. – 2005 Sep. 30., International Research Center of Japanese Studies, Office of Virtual Resources, Assistance Prof.
2005 Oct.1. – 2009 Jul. 31., Osaka City University, Graduate School of Literature and Human Sciences, Assistance Prof.
2009 Aug. 1. – 2017 Mar. 31., International Research Center of Japanese Studies, Office of Virtual Resources, Assistance Prof.
2017 Apr. 1. – , the University of Tokyo, the University Museum, Assistance Prof.
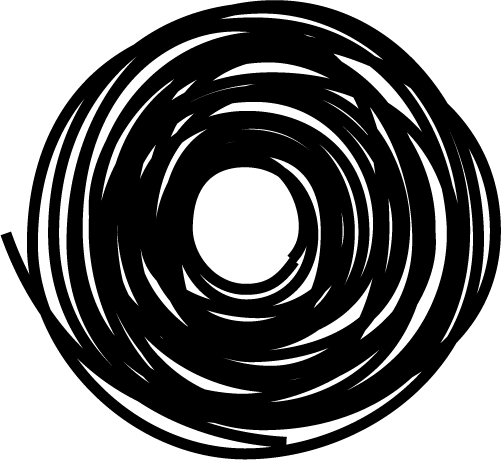

tinyState 疑似コルーチン・フレームワーク
オブジェクト指向プログラミングにおいて、オブジェクト一つ一つが完全に独立したコンテキスト実現できなければならない。コンテキストとは、他のコンテキストと並行・並列に動くプログラムであると考えるならば、オブジェクト指向プログラミングの終着点には並行・並列プログラミングがある。たとえば、スレッド。数千、数万といったスレッドを同時に生成したり、それも、生成されて、すぐに消滅するエフェメラルなスレッドが多くあると、システムに高負荷をかける。それだけではなく、高並列度のプログラミングは、確率的なバグを生みやすくデバギングの障害となる。これらの問題を解決するひとつの手法として、疑似コルーチン・フレームワークtinyStateの開発を行なっている。
サウンドスケープと展示システム
2021年の夏より、サウンドスケープを展覧会会場で展開する試みを行なっている。近年、インターネットやソーシャル・メディアの発達でビジュアル・プレゼンテーションが氾濫している一方で、音のメディアは影に隠れている。しかし、音は、視覚をも支配し、人間の慣性を動かす最も優れた感覚である。展覧会というビジュアル・メディアにサウンドスケープという音のメディアを加えることによって、どのように表現が広がるかを実験する。
私が所属する総合研究博物館では、二つの展覧会を行なってきた。
『疎と密 — 音景 x コレクション』2021年7月1日 〜 10月3日
『音景夜景 — トウキョウヘオモイヲハセル』2022年3月18日 〜 5月8日
また、研究室として、一つの演劇にサウンドスケープと楽曲を提供。
ジャンル・クロスⅡ<近藤良平×松井 周> 『導かれるように間違う』2022年7月10日(日)~18日
多チャンネルでの音声録音の方法、その処理システム、多チャンネルの音声再生のシステムを、本研究室開発のtinyStateフレームワークを使って構成、その性能の評価などを行なっている。
絵図の地理情報システム
測量図のみならず、地図・絵図をも含む様々な空間表現をベースマップとして利用可能なGISであるGLOBALBASEの開発を続けている。システムは2011年ごろには一定の完成度になった。国内と東南アジアを中心とした普及ミッションを続けてきた。しかし、システムの複雑度はGoogle Earthの比ではなく、その安定度をなかなか保てないという問題に直面し、中断している。tinyStateの発想はここからきた。
並行して、古地図の収集デジタル化を行なっている。総合研究博物館や米国議会図書館の伊能忠敬のコレクションのデジタルデータ収集、第二次世界大戦中の日本の航空写真の収取やその貼り合わせ・デジタル化をおこなった。カッシーニのフランス図のデジタルデータなどを収集し、GLOBALBASEの元となり得る様々な地図の収集を行ってきている。