教授
KARLIN, Jason G.
Professor
KARLIN, Jason G.
- アジア情報社会コース
研究テーマ
- メディア論・カルチュラル・スタディーズ
- ソーシャルメディア、データサイエンス、コンピューター・メディエイテッド・コミュニケーション (CMC)
- 区分:
- 学環所属(基幹・流動教員)
- ITASIA Program
Research Theme
- media and cultural studies
- social media, data analytics, and computer mediated communication (CMC)
- Position:
- III Faculty (Core & Mobile)
- 略歴
2002年 米国・イリノイ大学にて博士号(歴史学)取得
ミシガン州立大学講師、フロリダ大学助教授、東京大学社会科学研究所准教授(兼Social Science Japan Journalのマネージングエディター)を経て、
2008年 東京大学大学院 情報学環 准教授
2022年 東京大学大学院 情報学環 教授- 主要業績
詳細な業績はJason G. Karlin(Publications)をご覧ください。
- 関連リンク
- Biography
Jason G. Karlin’s background and academic journey are highly interdisciplinary, encompassing knowledge across several fields, disciplines, and methodological approaches. He earned his Ph.D. in History from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 2002. He is currently a professor at the University of Tokyo’s Interfaculty Initiative in Information Studies. His previous work includes positions as a Lecturer at Michigan State University (2001-2002), Assistant Professor at the University of Florida (2002-2003), and Associate Professor at the Institute of Social Science, University of Tokyo (2003-2008).
- Achievements
Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Edited by Patrick W. Galbraith and Jason G. Karlin. London: Palgrave, 2012.
Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History. Honolulu: University of Hawaii Press, 2014.
Media Convergence in Japan. Edited by Patrick W. Galbraith and Jason G. Karlin. Ann Arbor, MI: Kinema Club, 2016.
AKB48. Co-authored with Patrick W. Galbraith. London: Bloomsbury, 2019.
Law and Culture in Japan: Institutions, Justice, and Media. Edited by Mathieu Deflem, Hiroshi Takahashi, Dimitri Vanoverbeke, and Jason G. Karlin. Bingley, UK: Emerald Publishing, 2025.
- Related Links
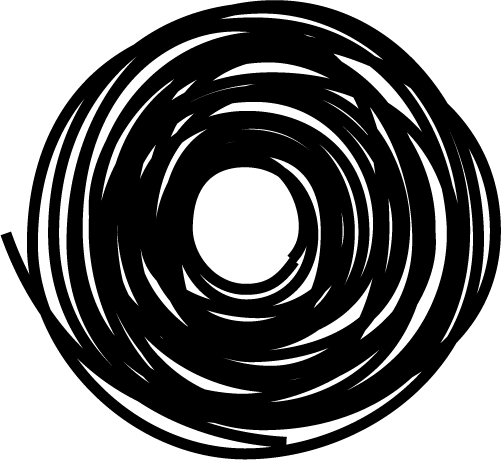


歴史学の博士号を持ち、文化、メディア、ジェンダー研究の交差点で独自の研究を展開しています。私のアプローチは、社会・文化理論とデジタルメソッドを組み合わせており、ウェブスクレイピング、データ集約、データサイエンスなどの手法を用いてメディアと文化研究分野の研究を進めています。これらの手法を通じて、デジタル時代におけるメディアの役割とジェンダー表象の深い探求を行い、学生たちは現代のメディア環境を批判的に分析する能力を養います。
アジア情報社会コースで提供される授業では、デジタルメディアの社会的影響を深く理解するための理論と実践的なスキルを学生に教えています。これには、デジタルコンテンツの生成、消費、そしてその社会的な文脈への影響を解析する方法が含まれます。異分野間のアプローチを取り入れることで、文化理論、社会学、心理学の視点からメディア研究を深め、デジタルツールを活用して新たな洞察を引き出しています。
私の教育と研究の目標は、学生たちがテクノロジーと文化の交差点で活動する知識人として成長するための支援をすることです。これにより、彼らは情報豊かで、より公正なグローバル社会の構築に貢献できるようになります。
主にアジア情報社会コースの学生を指導していますが、文化・人間情報学コースの博士課程学生の指導経験もあります。基本的に、修士論文または博士論文を英語で執筆する予定の大学院生のみを指導していますが、より学際的かつ国際的な視点を研究に取り入れたい日本語の学生の副指導も喜んで行います。
I hold a PhD in History but teach and research at the intersection of cultural, media, and gender studies. My research approach integrates critical media theory with digital methodologies, employing techniques such as computational content analysis, social network analysis, and data analytics to advance scholarship in media and cultural studies. Through these methods, I explore the complexities of media representation, digital culture, and gender dynamics in contemporary media ecosystems, equipping students with the critical thinking skills necessary to analyze and interpret today’s media landscapes.
In the courses offered in the Information, Technology, and Society (ITASIA) Program, I guide students through both theoretical frameworks and applied research methods essential for understanding the sociocultural implications of digital media. This includes critical approaches to analyzing the production, distribution, and consumption of digital content, as well as its broader societal impacts. By fostering an interdisciplinary perspective, I enhance media studies by incorporating insights from cultural studies, sociology, and digital humanities, utilizing computational tools to uncover new patterns and meanings in media texts and practices.
The aim of my pedagogy and research is to nurture scholars capable of navigating the complex interplay between technology, culture, and society. This approach enables them to contribute meaningfully to debates on media policy, digital ethics, and the role of communication technologies in shaping social realities.
While I primarily advise students in the ITASIA Program, I have also supervised doctoral candidates in the Culture and Human Information Studies course. Generally, I mentor graduate students who plan to complete their M.A. or Ph.D. theses in English, but I’m open to co-supervising students working in Japanese who wish to incorporate more interdisciplinary and global perspectives into their research.