准教授
植原 亮
Associate Professor
UEHARA, Ryo

- 文化・人間情報学コース
研究テーマ
- 科学哲学、哲学的自然主義、脳神経倫理学、自己制御、創造性、科学文化
- 区分:
- 学環所属(基幹・流動教員)
- Cultural and human information studies course
Research Theme
- Philosophy of Science, Philosophical Naturalism, neuroethics, self-control, creativity, scientific culture
- Position:
- III Faculty (Core & Mobile)
- 略歴
1978年 埼玉県生まれ
2008年 東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻相関基礎科学系(科学技術基礎論大講座)博士課程単位取得退学
2009年 日本学術振興会特別研究員PD(日本大学文理学部 ~2011年)
2011年 博士(学術、東京大学)
2012年 関西大学総合情報学部 准教授
2018年 同 教授
2025年 東京大学大学院 情報学環 准教授
- 主要業績
書籍
『科学的思考入門』、講談社、2025年
『人工知能とどうつきあうか』、勁草書房、2023年(共著、鈴木貴之編)
『遅考術』、ダイヤモンド社、2022年
『思考力改善ドリル』、勁草書房、2020年
『自然主義入門』、勁草書房、2017年
『生命倫理と医療倫理(第3版)』、金芳堂、2014年(共著、伏木信次他編)
『実在論と知識の自然化』、勁草書房、2013年
『道徳の神経哲学』、新曜社、2012年(共著、苧阪直行編)
『脳神経科学リテラシー』、勁草書房、2010年(共著、信原幸弘他編)
『脳神経倫理学の展望』、勁草書房、2008年(共著、信原幸弘・原塑編)
最近の論文
「徳認識論の中の知的創造性」『フィルカル:分析哲学と文化をつなぐ』2025年
「化学の哲学とは何か:科学哲学における科学」『科学・技術研究』2024年
”The way forward for neuroethics in Japan: A review of five topics surrounding present challenges” Neuroscience Research 2022年(E. Nakazawaらとの共著)
- 関連リンク
https://researchmap.jp/ryouehara
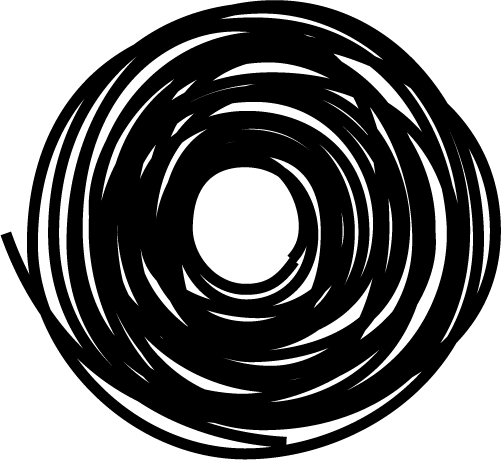

私の研究は、科学哲学を理論的な基礎に据えつつも、そこから科学技術と社会・人間との関係を広範に扱う学際的な領域へと主題的にも実践面でも発展を遂げてきました(これまでの研究業績について詳しくは上記のresearchmapで確認してください)。
ですので、研究室での指導を希望される場合も、上記の内容に関わるようなテーマであれば取り組むことが可能です。もちろん、相談や調整のうえで、新しいテーマに挑戦することもさしつかえありませんし、教員と共同のテーマで研究をすることもできます。
以下では、今後取り組むつもりの研究上のトピックをいくつか説明します。
・脳神経倫理学における発展的な課題としての自己制御
自己制御は、古代ギリシャ哲学以来、いわゆる節制として倫理的徳のひとつにも数えられてきた特性であり、現代においても意思決定の質や評価という実践的合理性の観点から注目されていますが、さらに脳神経科学的な手法によりアプローチされる対象でもあります。こうした多領域の接点において生じる様々な問題を検討するのがここでの課題です。
・創造性
創造性は大きく知的創造性と芸術的創造性に分けられますが、近年では人工知能の発展に伴い、人間独自の創造性の可能性が問われるようになりました。ここでは、創造性概念の再検討や科学教育におけるその意義の解明などを目指します。
・科学文化
科学と社会の健全な関係の構築を試みるうえでは、科学的思考の力の育成や科学コミュニケーションの活性化が重要ですが、それ先立ついわば「科学文化」と呼びうる土台も必要となります。C・P・スノーのいう二つの文化の橋渡しとなる第三の文化としての科学文化が、現代においていかなる形態として醸成可能であるかを考察します。他方でそれは、人文学の科学哲学的な再検討という課題に並行して取り組むことも意味します。
他にも、哲学的自然主義における大きな問題である「自然/人為」の区別の解消、とりわけ制度的対象の自然的基盤、現代版の人間本姓論の構想、D.Chalmersのいうテクノフィロソフィの可能性、などなど、やろうと思ってなかなか取り掛かれないでいるテーマも進めたいと考えています。